| 第21回 鹿児島県母性衛生学会 特別講演 |
環境温度が赤ちゃんの体温調節機構に及ぼす影響について ―赤ちゃんを発達障害・SIDSから守るために― 久保田産婦人科麻酔科医院 久保田史郎 |
要旨: 人間は体温を恒常に保つために、放熱機構と産熱機構を作動させ体温調節を行っている。安静時において、通常(快適)の環境温度下では産熱量に対して放熱量を調節する事で恒温状態を維持している。しかし、震えや汗をかく様な極端な低温/高温環境下では放熱量の調節に加えて、産熱亢進/産熱抑制という体温調節機構が作動する。例えば、日本の寒い分娩室で出生した赤ちゃんは、末梢血管収縮(放熱抑制)と啼泣(筋肉運動=産熱亢進)によって体温下降を防ぐ。一方、高温環境下では、放熱促進と産熱抑制によって高体温(うつ熱)から身を守る。ところで、分娩直後のカンガルーケア実施中のヒヤリハット事例(チアノーゼ・ケイレン・除脈・筋緊張低下)や事故(呼吸停止⇒脳性麻痺)の報告が相次いでいるが、それらの原因の一部が出生直後の「低体温⇔低血糖」が関与している可能性が高い事が分かった。また、初期嘔吐は生理的現象と考えられているが、出生直後の体温管理(保温)によって嘔吐が無くなった事から、初期嘔吐は胎内と胎外の環境温度差つまり分娩室の室温(低温環境)に原因がある事が分かった。 ところで、日本では乳幼児突然死症候群(SIDS)は原因不明の病気と考えられている。しかし、体温の研究から、SIDSは着せ過ぎ(放熱障害)・高温環境に伴う高体温(うつ熱)時の体温調節機構(放熱促進+産熱抑制)が原因と考えた。何故ならば、うつ熱時の体温調節機構は、発熱時と異なり、放熱促進(持続的末梢血管拡張=カテコラミン分泌↓)と産熱抑制(睡眠+筋弛緩+呼吸運動抑制)が作動するからである。SIDSが寒い冬に多いのは着せ過ぎによる。SIDSがうつぶせ寝に多い理由は、腹部からの放熱が妨げられ産熱抑制機構(筋弛緩)が働き、解剖学的に呼吸運動抑制、気道閉鎖(窒息)を起こし易いからである。扇風機のSIDS予防効果は、うつ熱防止(扇風機⇒放熱促進)に役立ったからと考えられた。 キーワード:恒温動物、自律神経、新生児、環境温度、低体温、体温調節機構、初期嘔吐、低血糖、重症黄疸、発達障害、着せ過ぎ、うつぶせ寝、高体温、うつ熱、乳幼児突然死症候群(SIDS)、扇風機、予防医学 緒言:当院では開業(1983年)以来、約11.000人の全ての赤ちゃんを対象に、出生直後の低体温・低血糖を防ぐための保育管理を行なってきた。当院の新生児管理の特徴は、生後2時間の保温(保育器内収容:34~30℃)と生後一時間目からの超早期混合栄養である。この方法は当院独自の保育管理法で、世界でも同様の管理はおそらく無いと思われる。この新しい管理法によって、発達障害の危険因子である早期新生児の低血糖症、重症黄疸、頭蓋内出血の発症をほぼ完全に予防する事が出来た。日本では、厚労省の後援によって母乳促進運動(カンガルーケア・完全母乳)が積極的に勧められているが、出生直後の赤ちゃんに体温管理(保温)がなぜ必要か、低血糖が今なぜ問題か、低血糖の原因と予防法について述べる。また、SIDSの原因について、うつ熱時の体温調節機構に焦点を当て、そのメカニズムを解説する。 対象と方法:当院で出生した正常成熟新生児を対象に、深部体温計(テルモ社:PD-3) (1,2,3)を用い、児の中枢(前胸部)と末梢(足底部)深部体温を、同時に30秒毎に測定した。また児の環境温度として室温と衣服内温度を測定した。その他、心拍数、呼吸数、経皮的酸素分圧(TCPO2)、および児の行動(睡眠/覚醒/啼泣)の観察を行った。 Ⅰ.分娩直後の低温環境が赤ちゃんの体温調節機構に及ぼす影響 (図Ⅰ) ■寒冷刺激のメリット・ディメリット 胎児は分娩を境に急激な環境温度の低下に遭遇し、生後1時間以内に約2.0℃〜3.0℃の体温下降を余儀なくされる(4)。胎内(38℃)と胎外(24~26℃)の環境温度差は出生直後の新生児にとって、“寒冷刺激”として呼吸を促進する上で重要な役割を果たす(5)。しかし、その寒冷刺激が強すぎた場合、赤ちゃんは低体温を防ぐために放熱抑制と産熱亢進という体温調節機構を作動させる。出生直後からの産熱亢進(啼泣=筋肉運動)が長引くと、酸素消費量・エネルギー消費量が通常より著しく増加する。日本の寒い分娩室で保温をしないで保育管理する事は、栄養摂取が未だ出来ない赤ちゃんにとって「低体温⇔低血糖」の発生率が増え、呼吸循環そして脳神経細胞の発育に不利益である。また、放熱抑制を目的に末梢血管が持続的に収縮すると、四肢のみならず消化管血流量も減少し、消化管機能に初期嘔吐などの悪影響が出る。 ■初期嘔吐のメカニズム 早期新生児の初期嘔吐は生理的現象と考えられている。しかし、体温の研究から、出生直後の低体温を防ぐための末梢血管収縮(放熱抑制)が真の原因である事が分かった。“食欲能”を示すと思われる吸啜反射は出生直後の低体温の時期では乏しく、低体温から恒温状態へと移行するにつれてその反射が強くなる。また、初期嘔吐は中枢と末梢の深部体温差が大きいほど多く観察される。出生直後からの末梢深部体温の下降、つまり足底部の血流量減少は消化管血流量を減少させ、腸管の蠕動運動を抑制し、初期嘔吐・胎便排泄遅延・胎便性イレウスなどの合併症を引き起こす。何故ならば、低体温状態(末梢血管収縮)では、①末梢血管抵抗の増大、②下肢から心臓に戻る静脈還流量の減少、③消化管から心臓へ戻る静脈還流量の減少、④消化管の血液循環量の減少、⑤消化管機能低下(蠕動運動の減少)、⑥胃内容消失時間の延長、⑦初期嘔吐、である。 |
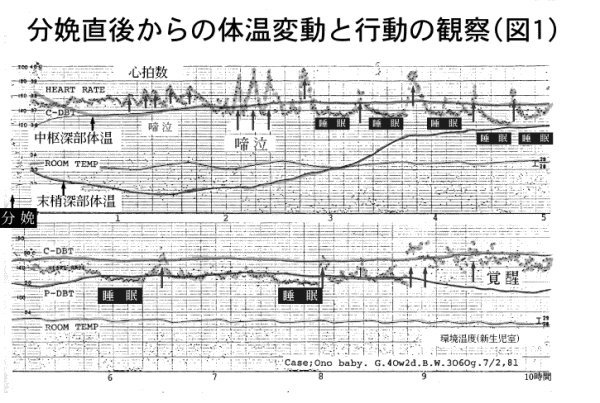 |
|
一般に、新生児は体温調節機能が未熟と考えられているが、出生直後から体温調節機構を巧妙に作動させ、低体温から恒温状態に移行する能力を備えている(図1)。出生直後の低体温の原因は、寒冷刺激による熱損失の方が産熱より優っているからである。日本の分娩室(24~26℃)では、出生直後の赤ちゃんは体温調節機構(放熱抑制+産熱亢進)の働きによって、生後5~8時間前後に恒温状態に移行するのが一般的である6)。しかし、出生直後の低体温から恒温状態への移行が遅れた時、児が何らかの理由によって低血糖に陥った時、体温調節機構が作動せず、「低体温⇔低血糖」の悪循環が成立する。この悪循環こそが、カンガルーケア実施中のヒヤリハット事例7)8)・脳の栄養障害(発達障害)9)の原因と考えられる。 Ⅱ.体温調節機構に異常を招いた低血糖症の一例 (図2) 新生児の体温調節に関する研究を始めた時期(1981年)に、偶然にも遭遇した低血糖症の一例を紹介する。母親に妊娠糖尿病などの合併症はなく、児は3036g、正常満期産児、新生児仮死もない。分娩室・新生児室の室温は24~26℃であった。この症例の特徴は、図1と異なり、生後2~6時間目に中枢/末梢の深部体温が並行して下降している事である。生後4時間目に中枢深部体温が36℃以下に下降したにもかかわらず、放熱抑制/産熱亢進のための体温調節機構が全く作動していない。心拍はサイレント(平坦)であり、啼泣(筋肉運動)もない静かな状態が記録された。この体温変動の特徴は、無脳児10)の体温変動と同様のパターンを呈している事である。体温の異常に気づき血糖値を測定すると、重度の低血糖(8mg/dl)であった。速やかな治療、すなわち保育器内収容(①保温、②酸素投与、③糖水の経口摂取)により児は後遺症を残すことなく回復した。体温の測定中でなければ異常(低血糖症)に気付かず、脳に重篤な後遺症を残した可能性の高い症例である。当院が出生直後の体温管理(保温)と生後一時間目からの超早期混合栄養法にこだわる理由は、この低血糖症の一例に遭遇したからである。 |
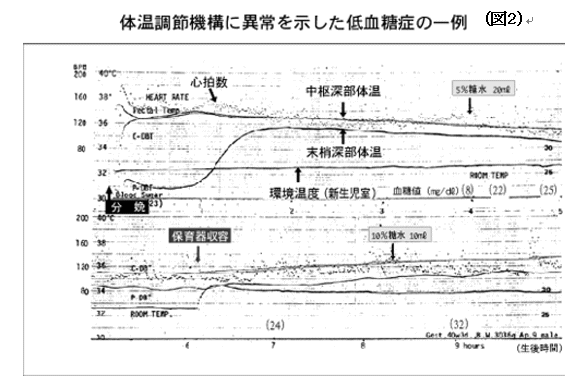 |
Ⅲ.低血糖はなぜ危険か 脳障害の危険因子として新生児仮死、重症黄疸、低血糖が一般にも知られているが、最も警戒すべきは出生直後の低血糖である。その訳は、新生児仮死・重症黄疸は異常所見が肉眼的に外から見えるために早期診断・早期治療が可能である。しかし、低血糖は血糖検査をしない限り診断がつかないために、出生直後の低血糖が見逃されている可能性があるからである。分娩時の低酸素血症や重症黄疸に対しての診断・治療は確立されたが、正常新生児に対して血糖検査をする産科施設は一部を除きほとんど行なわれていない。新生児の低血糖が恐い理由は、痙攣などの症状がなく、見えない所(血管の中)で低血糖が静かに進行し脳神経細胞の発育に害を与えるからである。授乳によっていずれ低血糖は正常に回復したとしても、障害を受けた脳神経細胞の回復は望めない11)12)。低血糖による脳障害を防ぐには、低血糖の早期診断・早期治療は勿論の事、それ以上に低血糖にならない様に保育管理することが重要である13)。低血糖が脳神経細胞の発育に悪い事が分かっているにもかかわらず、出生直後の低血糖に対する予防策は全く進んでいない。その理由は、低血糖による脳神経障害(発達障害)は生後2~3年経たないと児の神経学的異常に気づかないためと考えられる。 ■低血糖は発達障害(自閉症スペクトラム)の危険因子のひとつ 我国の周産期医療は目覚しい進歩をしたと報告されている。しかし、近年の発達障害児とりわけ自閉症スペクトラムの異常な増加に対する周産期側の反応は鈍い。自閉症は精神科医、小児科医、生理学者などが中心となって原因解明に向け研究が進められているが、周産期側からの疫学調査・研究は無いに等しい。その訳は、自閉症は先天的な脳の機能障害であり、多くの遺伝因子が関与していると報告されているからだと考えられる。しかし、自閉症スペクトラムに関するこれまでの疫学調査は、「低血糖説」を支持する内容が報告されている9)14)。米国15)では1980年代、福岡市16)では1990年代後半から発達障害が異常に増加しているが、その増加率(平成元年33人、平成10年182人、平成19年263人)の早さから自閉症の原因を先天的な遺伝因子だけで説明することは困難である。注目すべき点は、母乳促進運動がスタートして3~5年後に、米国・日本(福岡市)で発達障害が爆発的に増加している事である。自閉症は診断基準の変更をきっかけに増加しているという米国の調査もある。しかし、福岡市の発達障害児数の推移が、1994年(日本語版1995年)DSM-4改訂後も著しく増えていることから周産期側からの調査研究が急務である。 Ⅳ.低血糖の原因と危険因子(図3) 1993年、厚生労働省がWHO/UNICEFの「母乳育児を成功させるための10か条」を後援した事によって、母乳推進運動は全国で積極的に展開されている。しかし、10か条の中で第4条(カンガルーケア)と第6条(完全母乳)を日本で忠実に実行すると、赤ちゃんは出生直後に「低体温⇔低血糖」に陥る危険性が増える。 ■ WHO/UNICEFの「母乳育児を成功させるための10か条」の問題点 第4条:母親が分娩後、30分以内に母乳を飲ませられるように援助すること 分娩室の室温が出生直後の新生児にとって快適な環境温度(中性環境温度:30℃~32℃)に調整されていれば、第4条は何ら問題ない。しかし、日本の分娩室は大人に快適(24℃~26℃)な環境温度に調整されている。胎内と胎外の温度差(約13℃)は出生直後の赤ちゃんにとって寒すぎるため、児は一過性の低体温となる。その後、赤ちゃんは体温調節機構(放熱抑制+産熱亢進)を作動して、低体温から恒温状態に移行する。しかし、第4条(カンガルーケア)の管理法を間違えば、低体温は進み恒温状態への移行が遅れる。出生直後からの低体温が持続した場合、自律神経は低体温から恒温状態に移行するための体温調節機構(放熱抑制+産熱亢進)を優先するため、生命維持装置(呼吸・循環・消化管・内分泌など)に異常が発生しても自律神経機能による自然回復は望めない。生後30分以内のカンガルーケア中に、全身チアノーゼ・筋緊張低下・徐脈、ケイレン、呼吸停止などの危険な症状が発生すると報告がある7)。それらの一部の原因は、出生直後の「低体温⇔低血糖」が児の生命維持装置に異常を招いた結果と考えられる。 |
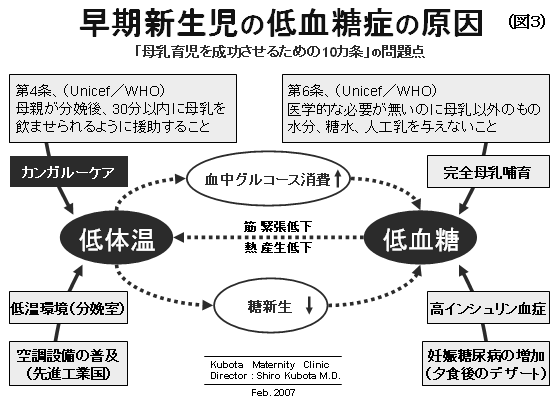 |
第6条:医学的な必要がないのに母乳以外のもの、水分、糖水、人工乳を与えないこと 母乳が出生直後から十分(基礎代謝量)に出るのであれば、この第6条も何ら問題ない。新生児が生きるために必要とされる1日の基礎代謝量は50kcal/kgと教科書17)にあるが、出生初日の母乳分泌量は初乳が滲む程度でエネルギー源としての母乳は殆ど出ていない。特に初産婦の場合、生後3日間の母乳分泌量は基礎代謝量の約1/3と報告18)されている。即ち、母乳以外の糖水や人工ミルクを全く飲ませない完全母乳で哺育した場合、赤ちゃんは真に飢餓状態である。新生児早期の低血糖、重症黄疸、脱水、極度の体重減少などの原因は、児の摂取カロリーが基礎代謝量に満たない極度の栄養不足が原因で発生した非生理的な現象(病気)と考えるべきである19)。 ■ 低血糖促進因子:胎児の「高インシュリン血症」 妊娠糖尿病の母親から生まれる新生児(糖尿病母体児)の30~40%は、生後1~2時間後に低血糖を起こすと報告されている。低血糖のメカニズムは母体の高血糖が胎児に移行するために胎児膵臓は過形成され、インスリン分泌が亢進しているからである。分娩直後、臍帯切断と同時に一過性の血糖値の低下が見られるが、高インスリン血症の赤ちゃんの血糖値はさらに下降し、また低血糖から正常血糖値への回復に時間を要す。インスリン値が4μU/ml前後に低下・安定するまでは、血糖測定を怠らない方が安全との報告がある20)。当院で経膣分娩で生まれた赤ちゃんの臍帯血インスリン値4μU/ml以上は、145人中20人(14%)であった。対象の145人に妊娠糖尿病と診断された妊婦は一人もいない。インスリン値が4μU/ml以上であった妊婦の特徴は、夕食後のデザート(果物)を習慣的に食べる妊婦さんに多く見られた。高インスリン血症の赤ちゃんは妊娠糖尿病児・肥満児だけでなく、正常新生児にも多い事が分かった。以上の理由から、低出生体重児だけでなく、全ての新生児に対して低血糖に対する予防策が重要である。 Ⅴ.日本の分娩室は、赤ちゃんに快適か?(図4) 日本の分娩室(24~26℃)は裸の赤ちゃんにとって快適かどうかを調べるために低温と高温の二つの異なった環境温度を準備し、出生直後の低体温から恒温状態へ移行するまで体温変動の違いを観察した。通常の分娩室(24~26℃)で管理した11名をcool群(上段)、出生直後より生後2時間まで保育器内(34→30℃)に収容し、その後に新生児室(24~26℃)に移した10名をwarm群(下段)とした ■cool群とwarm群における体温調節の違い: 中枢深部体温の特徴:cool群では、C-DBT(直腸温)は生後約42分で最低(平均36.2℃)となり、平均2℃の体温下降が観察された。warm群では生後28分で最低(平均37.2)となった。生後2時間の体温管理(保温)の有無によって、両群の体温下降に約1.0℃の違いが認められた。この僅か1.0℃の体温下降の違いは、早期新生児の体温調節、糖代謝にどんな影響を及ぼすのか、出生直後に低体温となった赤ちゃんは、どの様なメカニズムで恒温状態に移行するのか、両群の体温調節の違いについて解説する6)。 |
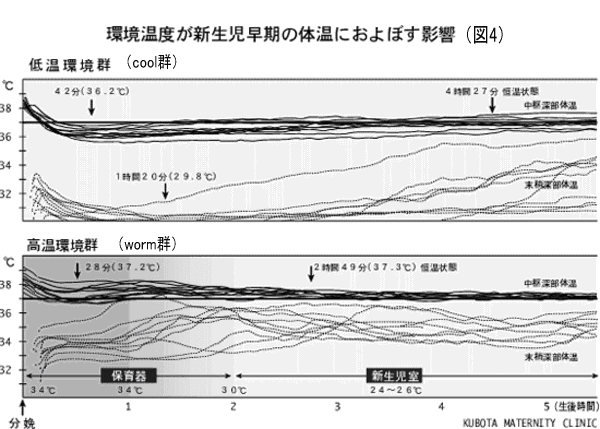 |
■体温調節メカニズムの特徴 出生直後の分娩室の環境温度の違いによる体温調節機構の特徴は、中枢深部体温(C-DBT)に連動した末梢深部体温(P-DBT)の変動が両群間で大きく異なる点である。中枢と末梢の体温較差は産熱量を、P-DBTの変動は末梢血管の収縮/拡張つまり放熱量を意味する25)。cool群では出生直後よりP-DBTの急激な体温下降(最低:平均29.8℃)が全例に観察された。cool群の特徴は、①中枢と末梢の体温較差が大きいこと、②生後5時間以上が経過したにもかかわらず、P-DBTの体温回復にバラツキがあり、約半数(6/11人)が32℃以下、つまり末梢血管が持続的に収縮していることである。 一方、warm群の特徴は、①中枢と末梢の体温較差が少ない、②P-DBTにリズミカルな体温変動が出生直後から全例に見られた事である。 出生直後の体温調節のメカニズムは、放熱を防ぐための末梢血管収縮と熱産生を増やすための啼泣(筋肉運動)によって低体温から恒温状態へと移行する。体温下降の著しいcool群の赤ちゃんは、産熱量を増すためにwarm群より多くの糖分と酸素を消費する。また放熱抑制を目的に末梢血管が持続的に収縮することは、足底部のみならず消化管の血流量を減少させ、臨床的には腸管の機能障害(初期嘔吐・胎便排出遅延・胎便性イレウス)を引き起こす。 ■日本の分娩室は、赤ちゃんにとって寒すぎる warm群の赤ちゃんの体温調節機構の特徴は、中枢深部体温(C-DBT)に連動した末梢深部体温(P-DBT)のリズミカルな体温変動が早期から認められた事である。哺乳動物に不可欠な消化管機能(蠕動運動)は、このリズミカルな体温変動つまり恒温状態で機能を正常に発揮する。warm群で生後間もなく吸啜反射が見られ、初期嘔吐もなく、生後1時間目からの糖水の経口摂取が可能になった理由は、新生児が恒温状態に安定しているからである。P-DBTのリズミカルな体温変動は、寒冷刺激に対する熱産生(カロリー消費)の増加や、熱刺激による発汗を伴わない、赤ちゃんにとって安全で快適な環境温度(中性環境温度)である事を物語っている。日本の分娩室(cool群)は、出生直後の裸の赤ちゃんにとって寒すぎる 事が分かった。 Ⅵ.環境温度が糖代謝(血糖値)に及ぼす影響(図5) 出生直後の環境温度の違いが早期新生児の血糖値に及ぼす影響について、次の3群で比較検討した。A群:通常の室温管理(cool群)、B群:生後2時間の保温(warm群)、C群:生後2時間の保温(warm群)+超早期混合栄養をした群である。A群、B群の栄養法は、生後8時間目に5%糖水20ml、C群の超早混合栄養法は生後1時間目に5%糖水20ml、その後4、7時間目に人工乳20mを飲ませた。 成績:血糖値はA群で最も大きく下降した。その後の上昇は生後9時間目まで認められなかった。B群は生後2時間の保温のみで血糖値の低下に抑制効果が認められた。A群とB群の血糖値低下の相違は、両群の低体温から恒温状態に至るまでの体温調節(産熱)に要した消費エネルギー量と糖新生の違いに影響したものと考えられる。さらにA群は生後8時間目に5%糖水20mlを摂取したにもかかわらず血糖値の上昇を認めなかったが、保育器内に収容したB群、C群では、糖水・人工乳摂取後にすみやかな血糖値の上昇を認めた。このことはcool群とwarm群における分娩直後から恒温状態に至るまでの体温調節の違い、つまりA群のP-DBTの持続的な低下、B群のリズミカルな体温変動、この体温変動の違いが消化管機能に影響を与えたためと考えられる。即ち、A群は中枢と末梢の体温較差が著しく、またP-DBTの低下が長時間に及んでいることから、A群はB群に比べ消化管血流量が少ないことが予測される。つまり消化管血流量の良、不良が、両群の消化/吸収/蠕動運動などの消化管機能に違いをもたらしたと考えられた。 |
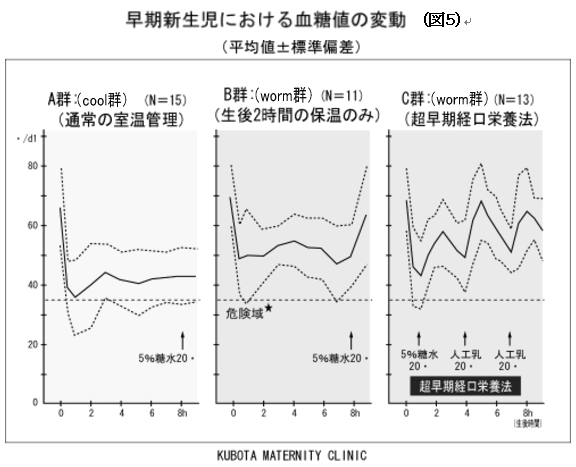 |
A群の糖水摂取後に血糖値上昇が見られなかった理由は、糖水の胃内容消失時間がA群はB群より長時間を要したためである。その証拠は、両群の胃内容物(糖水)の胃内容消失時間を超音波断層装置で観察すると、B群の消失時間は1時間以内であり、A群の胃内糖水量は1時間経過後もほとんど減少していなかったからである。B群の糖水摂取後に血糖値が速やかに上昇した理由は、糖水が胃から小腸に短時間に移動し腸管から吸収されたからである。初期嘔吐が高温環境群に無い理由は、胃内容消失時間が早く、授乳時に胃内が空っぽになっているからである。以上の成績から、生後2時間の保温(warm群)と超早期混合栄養をしたC群は、早期新生児の低血糖症をほぼ完全に予防し得ることが分かった。 Ⅶ.赤ちゃんにも予防医学を 新生児早期の“初期嘔吐”はこれまで生理的現象として当然の様に考えられている。しかし、胎内と胎外の環境温度差(約13℃)を少なくする生後2時間の体温管理(保育器内収容:34〜30℃)によって、この初期嘔吐は著しく改善し、生後1時間目からの超早期経口栄養が可能となった。その結果、胎便排出は促進され、低血糖症や重症黄疸は激減した。新生児早期の消化器系統の一部の異常は、主に出生直後の低体温がもたらした末梢血管収縮による腸管の血流量低下に影響されていたと考えられる。体温調節つまり放熱防止のための末梢血管収縮は、恒温動物であるヒトの体温調節機構には有利に働くが、早期新生児の消化管機能の面においては不利益と言わざるを得ない。すなわち、出生直後の赤ちゃんは低体温から身を守るために、消化管機能を犠牲にしてまで体温調節機構を優先的に作動させている。この体温調節機構に重過ぎる負荷(寒冷刺激)を与えないように体温管理をし、さらに生後数日間の栄養不足を人工ミルクなどで補充することによって、発達障害児の原因となる低血糖症、重症黄疸、Vit-K欠乏性出血症(頭蓋内出血)、などの合併症を予防し得る事が分かった19) 21) 22)。 Ⅷ.高温環境が乳幼児の体温調節機構に及ぼす影響 (図6) ■SIDSは着せ過ぎ・温め過ぎによる高体温(うつ熱)が原因 人間は、命ある限り『熱』を産生し続ける。しかし、何らかの理由で熱産生が減少し続けた時、生命の存続は危ぶまれる10)。安静時(睡眠中)の産熱量は、主に環境温度(衣服内)に左右される。正常新生児の体温は、寒い時には “啼泣”(筋肉運動)によって産熱量を増す。暑い時には筋緊張低下と呼吸運動抑制によって熱産生を低下させる。即ち、産熱量は高温環境下で筋肉を弛緩させ眠っている時が最も少ない。着せ過ぎなどによって衣服内の環境温度が上昇し続けた時、児は高体温(うつ熱)を防ぐための体温調節機構(放熱促進+産熱抑制)を作動させる。それがSIDSの原因である。 ■高体温(うつ熱)の原因 睡眠中の乳幼児に帽子・靴下・毛布などを着せ過ぎると、放熱が妨げられ衣服内温度が上昇し、児の高体温化(うつ熱)が進む。この時、児は体温上昇を防ぐための体温調節機構(放熱促進+産熱抑制)を作動させる。うつ熱時に見られる発汗、そして睡眠・呼吸運動抑制・筋緊張低下などの現象は、体温調節機構の働きによる。衣服内温度が上昇すると睡眠に伴う体温下降は認められず、寒さを感じない赤ちゃんは眠りから覚めない(覚醒反応遅延)。睡眠からの覚醒の遅れは、放熱し続ける自分の熱で衣服内温度を上昇(蓄熱)させ、児の高体温化をさらに促進する。この時、うつ伏せ寝・暖房器具(ホットカーペット)・熱過ぎる人工乳などで体の外側/内側から児を温めると、高体温化(うつ熱)はさらに加速する。 ■SIDSのメカニズム 睡眠中に着せすぎ(放熱障害)などによって高体温化が進むと「うつ熱」を防ぐための体温調節機構(放熱促進+産熱抑制)が働く。先ず、放熱促進を目的に末梢血管を拡張させ発汗を促す。体温調節を目的に末梢血管が拡張し続けると、交感神経機能は抑制(カテコラミン分泌↓)され、心機能は低下する。放熱促進だけで「うつ熱」が改善しない場合には、放熱促進に加え産熱抑制機構(睡眠+筋弛緩+呼吸運動抑制)が作動する。その結果、児の肺換気量は減少し、血中の酸素濃度は次第に低下する4)。恒温動物にとって高温環境が危険な理由は、人間が睡眠中に「うつ熱」状態になった時、生命維持装置を司る自律神経機能は呼吸循環器系の調節より、体温を恒常に保つための体温調節機構(放熱促進+産熱抑制)の方を優先的に作動させるからである。睡眠時のうつ伏せ寝が危険な理由は、解剖学的にうつ熱時の筋弛緩作用が呼吸運動を抑制し、また気道閉鎖(窒息)を起こし易いからである。SIDSは病気ではなく、乳幼児が放熱促進(交感神経抑制⇒心機能低下)と産熱抑制(睡眠+筋弛緩+呼吸運動抑制)を強いられる高温環境(着せ過ぎ)に遭遇した時に発生する23) 24) 25) 26)。 ■SIDS予防法:着せ過ぎ・暖めすぎに注意 乳幼児をSIDSから守るためには、「着せ過ぎ・温め過ぎに注意」と報告されている27) 28)。SIDSは仰向け寝運動29)により減少したが、睡眠中の環境温度(衣服内)が自分の体温より上昇した時、SIDSは体位に関係なく、仰向け寝でも発生する。SIDSが寒い冬に多く発生するのは、着せ過ぎ等によって衣服内温度が上昇して、児を「うつ熱」状態にするからである。1歳未満の乳幼児に多い理由は、帽子・靴下を自分で脱ぎ、暑い布団の中から逃げ出すことが出来ないからである。SIDSで亡くなった乳幼児に発汗が強く見られるのは「うつ熱」であった証拠である。死亡後、時間が経過しているにもかかわらず児の体温が高い理由は、着せすぎによって衣服内温度が高く、児は高温環境で保温された状態で亡くなっているからである。SIDSの原因が「うつ熱」である事を裏付ける資料として、扇風機のSIDS予防効果がある。そのメカニズムは、扇風機によって放熱を促進し高体温(うつ熱)を防止したためと考えられる。(Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162(10):963-968) ■米国:SIDSリスクについて再警告 NICHD Alerts Parents to Winter SIDS Risk and Updated AAP Recommendations January 18、2006 乳幼児突然死症候群(SIDS)で死亡する乳児の数は,寒冷期に増加する。多くの親は乳児の身体を保温するため就寝時に厚着をさせたり,余分に毛布をかけたりする傾向がある。米国立小児保健・ヒト発育研究所(NICHD)のDuane Alexander所長は,SIDSリスクを高めるため,親や養護者は睡眠時の厚着や毛布のかけすぎを避け,室温を上げすぎないように注意すべきであると、警告した。 |
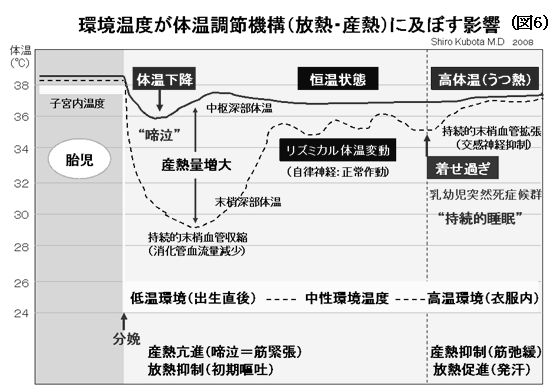 |
結語: ■お産の歴史 1993年、厚労省がWHO/UNICEFの「母乳育児を成功させるための10カ条」を後援したのを契機に、出生直後の新生児管理は様変わりした。我国の歴史的な「産湯」の習慣は無くなり、生後30分以内のカンガルーケアが当たり前となった。栄養面においても、乳母・もらい乳の慣習も消え、母乳以外の糖水・人工乳を与えない完全母乳栄養法が赤ちゃんに優しいと考えられる様になった。ところが、出生直後の寒い分娩室でのカンガルーケアと母乳が満足に出ない生後0~3日間の完全母乳栄養法は、低体温・低血糖・重症黄疸などの合併症を増やし児に不利益である。早期新生児の重症黄疸、低血糖症は脳性麻痺の危険因子である事は医学的常識である。しかし、それらの治療法は研究されているが予防法についての報告は無いに等しい。我国の障害児の発生率は6~8%といわれ、年々増加している。ここで述べた出生直後の体温管理と超早期混合栄養法こそが重症黄疸、低血糖症を防ぐ障害児発生防止策である。母乳は児にとって最高の栄養源であることに異論はない。しかし、母乳が十分に分泌し始めるまでの生後3日間の極度の栄養不足は真に飢餓状態である。Cornblath30)、永井31)らは出生直後の体温下降を最小限に止め、血糖値を正常に保持することが早期新生児の基本的管理と述べている。 昔、日本のお産には「産湯」と「乳母」が常識であった。産湯は現代の保育器(室温を上げる)の役割を、乳母は母乳が十分に出始めるまでの期間、あるいは母乳が出ない人のために、今日の人工乳の役割を果たしていたと考えられる。産湯と乳母は、日本の産婆さんが考案した新生児管理における「予防医学」であった。近年の発達障害の急激な増加は、その歴史的な予防医学が日本から消えた事が一因と考えられる。 ■体温管理(保温)の目的 当院では生後2時間、赤ちゃんを保育器内(34~30℃)に収容する。その体温管理の目的は、(1)低体温を防ぎ、産熱亢進に要する無駄なカロリー消費を少なくし、低血糖を防ぐ、(2)肝グリコーゲン分解による糖新生を促し、低血糖を防ぐ、(3)初期嘔吐を予防する事によって超早期経口栄養法を確立し、低血糖症・脱水・電解質の異常などを防ぐ、(4)栄養不足の改善と胎便排出の促進によって重症黄疸・頭蓋内出血を防ぐ、(5)低体温から恒温状態への移行を早め、自律神経機能が体温調節のみならず、生命維持装置(呼吸・循環・消化管・内分泌など)の機能を正常に作動させるためである22)。 ■人間は恒温動物であり哺乳動物である。 現代の新生児管理の問題点は、哺乳動物である母乳促進運動を優先し、恒温動物である体温管理の重要性を忘れている事である。哺乳動物の消化管機能(吸啜・消化・吸収・排泄)は自律神経によって調節されている。その自律神経機能は低温環境下では、体温の恒常性を保つための体温調節機構(放熱抑制⇒末梢血管収縮)を優先するため、消化管機能に悪影響(消化管血流↓⇒初期嘔吐・胎便排泄遅延・胎便性イレウス)を及ぼしている。母乳促進運動の第一歩は、いかに早く母乳を飲ませるかではなく、いかに早く低体温から恒温状態に移行させるかが新生児管理の基本である。恒温動物である人間の自律神経機能は、人間が恒温状態の時にはじめて、生命維持機構(呼吸・循環・消化管・内分泌など)の調節を可能にするからである。 稿を終わるに当たり、本学会で特別講演の機会を与えて頂きました鹿児島県母性衛生学会会長 堂地 勉教授に深謝いたします。 尚、本稿は日本新生児学会総会(第17回、第18回、第34回、第39回)、日本母乳哺育学会(東京:2001年)、第8回日本SIDS学会(大阪:2002年)で発表、日本小児麻酔学会(福岡:2003年)、日本臨床体温研究会(札幌:2004年)、鹿児島県母性衛生学会(鹿児島:2008年8月)で講演したものをまとめたものである。 参考文献: 1.Fox RH, Solman AJ, et al:A new method for monitoring deep body temperature from the skin surface.Clin Sci、44:81-86,1973. 2.戸川達男:深部体温計(Ⅰ)-基礎—電子医学、11:55—60,1976 3.辻隆之.深部体温計−臨床−電子医学、11:61—67,1976. 4.久保田史郎、他:新生児における体温変動の観察.産婦人科治療, 39:463-469,1979. 5.小川次郎編:新生児学−基礎と臨床—、東京、朝倉書店、p138,1978. 6.Kubota, S.et al. Homeothermal ajustment in the immediate postdelivered infant monitored by continuous and simultaneous measurement of core and peripheral body temperatures.Biol Neonate;54:79-85,1988. 7.中村友彦:カンガルーケアの留意点、日産婦医会報、1月2007. 8.廣瀬志奈、他:一事例から考えるカンガルーケアの検討、母性衛生、 49(3):184,2008 9.高橋 信也、他:症候性低血糖を来たした完全母乳栄養児の1例. 日本小児科学会雑誌.110(6):789~793,2006. 10.中野仁雄、久保田史郎:新生児の深部体温モニタリング、臨床婦人科産科、 37(8):555-558、1983. 11.Winick M: Malnutrition and brain development. J.Pediatr. 74 : 667-679,1969 12. Lewis P.D. :Nutrition and anatomical development of the brain. (Mal)nutrition and the infant brain. Ed.by van Gelder N.M., Butterworth R.F., Drujan B.D.,Wiley-Liss, New York:89-109,1990. 13.Craviote J,. DeLicardie E., Birch H.G. : Nutrition, growth and ecologic study.Pediatrics,38 : 319-372,1966 14. Dilek Yalnizoglu a,*, Goknur Haliloglu:Neurologic outcome in patients with MRI pattern of damage typical for neonatal hypoglycemia, Brain & Development,29:285-292,2006. 15.F.EdwardYazbak,M.D.,F.A.A.P.AutismintheUnitedStates:aPerspective,JournalofAmerican Physiciens and Surgeons:8(4):103-107,2003. 16.新規受付児の障害種別(発達障害)の年次推移(平成19年度:福岡市資料) 17.仁志田博司:新生児に必要な栄養量. 新生児学入門医学書院,173-174,1988. 18. 草川功、他:母乳管理と母乳分泌.日本新生児学会雑誌,31:719,1995. 19.久保田史郎:環境温度が赤ちゃんの体温調節機構に及ぼす影響についてー赤ちゃんを発達障害・SIDSから守るためにー: 臨床体温、23(1):20-34,2005 20.後藤幹生、他:糖尿病母体から生まれた新生児の低血糖症 その重症度・遷延性を予測する試み、第13回静岡内分泌同好会(口演発表)静岡市,2001. 21.久保田史郎、他:重症黄疸などを防ぐ新生児の新管理法,Medical Asahi:80-83、2002 22.久保田史郎:安産と予防医学『THE OSAN』紀伊國屋書店福岡本店,福岡、2000. 23.久保田史郎、他:SIDSの原因は放熱障害か—新生児の体温調節と睡眠/呼吸/循環機能からー.第8回SIDS学会抄録集,2002 24.久保田史郎:乳幼児突然死症候群は着せ過ぎ(放熱障害)が原因.日本新生児学会雑誌(学術集会号) 39:437,2003. 25.久保田史郎:環境温度が赤ちゃんの体温調節機構に及ぼす影響—乳幼児突然死症候群の原因は放熱障害—.日本小児麻酔学会誌(教育セミナー)、9:41—43,2003 26. 久保田史郎:乳幼児突然死症候群はうつ熱時の「産熱抑制」が原因 体温のバイオロジー(LISA増刊)メディカル・サイエンス・インターナショナル社発行:86—90,2005 27.Bacon,C.Scott,D.& Jones,P:Heatstroke in well-wrapped infants Lancet; i:422-425,1979. 28. Stanton,AN.Scott, DJ.& Dowmnham,MAPS.Is overheating a factor in some unexpected infant deaths? Lancet; i:1054-1057,1980. 29. 船山真人:SIDSとうつ伏せ寝.小児内科,30:521—524,1998. 30.Cornblath M:Neonatal hypoglycemia. Pediatric current therapy Philadelphia W.B.Saunders Co ;803-805,1995. 31.永井文作、他:出生早期の直腸温と血糖値の推移.日本新生児学会雑誌,15: 468〜474,1979. |