| 厚労省の「授乳と離乳の支援ガイド」に警鐘! |
母乳育児3点セットの “落とし穴” |
| 久保田産婦人科麻酔科医院(福岡市) 院長 久保田史郎 |
| はじめに 国の「授乳と離乳の支援ガイド」は、厚労省が母乳育児を進める目的で、WHO/ユニセフが1989年に出した「母乳育児を成功させる為の10カ条」の指針を参考に2007年に策定された。10カ条のなかでも、母乳育児の3点セット(第4条:出生直後のカンガルーケア、第6条:完全母乳、第7条:母子同室)は支援ガイドの柱である。ところが、出生直後のカンガルーケア(early skin to skin contact:STS)中、そして母子同室中に、新生児の心肺停止事故が全国で相次いでいる事が学会誌に報告された。また、福岡市では、厚労省の母乳育児推進運動(完全母乳)がスタート(1993年)した数年後から発達障害児が増え始め、とりわけ、カンガルーケア(STS)導入後の2003年以降から自閉症児が驚異的な勢いで増加し続けている事が分かった。 日本で心肺停止事故・発達障害児が増え続ける理由は、母乳育児3点セットの長所(利点)ばかりが世に知れ渡り、出生直後のカンガルーケア・完全母乳・母子同室の短所(危険性)が国民に何も知らされていないからである。国(厚労省)はカンガルーケア(STS)中に心肺停止事故が多発している事の報告を受けたにもかかわらず、充分な調査もせず、事故原因は不明であり、カンガルーケアそのものが原因ではないと発表した。国(厚労省)・新生児科医の過ちは、出生直後のカンガルーケア(STS)がNICU入院児のカンガルーケアと同様の “保温効果” があると勘違いし、出生直後の体温管理(低体温の予防)を怠っている事である。国・新生児科医は、なぜNICU入院児のカンガルーケアに事故事例がなく、出生直後・母子同室中のカンガルーケア(STS)に心肺停止事故が多発するのかを調査し、出生直後のカンガルーケア(STS)の危険性を一刻も早く、国民に知らせるべきである。 出生直後のカンガルーケアがNICU入院児のカンガルーケアに比べ危険な理由は、①児は分娩直後に寒冷刺激(胎内と胎外の環境温度差=約13℃)を受け、低体温(冷え性)に陥り易い、②寒冷刺激は四肢の末梢血管・肺動脈血管を同時に収縮させ、最も危険な新生児肺高血圧症(チアノーゼ=低酸素血症)を誘発する。③分娩室・母子同室の環境温度が児に寒すぎる為、エネルギー(糖)消費が増し、低血糖症に陥り易い、④出生初日は、児のエネルギー源である母乳がほとんど出ないために、完全母乳だけでは児は飢餓状態(低血糖症)に陥り易い、⑤ベッド上の母親の体位が水平位のため、児が “うつ伏せ寝”の状態となり、気道閉鎖(窒息死)を起こし易い、⑥カンガルーケア中の児はタオル・毛布などで全身が覆われているために、児の全身状態の観察が全く出来ない。児の異常に気付くのが遅れ心肺停止に至る。つまり、出生直後のカンガルーケアは、児にとって危険極まりない新生児管理法である為、事故は起こって当たり前である。 出生直後のカンガルーケア(STS)を推奨する新生児科医だけで構成されたカンガルーケア・ガイドラインワーキンググループは、南アフリカのザンビア(後発開発途上国=最貧国)の臨床データを引用し、カンガルーケア(STS)は保育器よりも体温上昇作用の効果があると報告している。しかし、カンガルーケアの体温上昇作用が真実ならば、日本で心肺停止事故や発達障害児が急激に増える筈がない。何故ならば、カンガルーケアの体温上昇作用(低体温の予防)が真実ならば、新生児の呼吸循環動態を安定化し、糖新生を促し、低血糖症を予防するからである。ところが、出生直後のカンガルーケアが普及し始めてから心肺停止事故や発達障害児が急激に増え続ける社会現象は、出生直後のカンガルーケア(STS)に体温上昇作用(保温効果)が無い事を暗に物語っているのである。 ワーキンググループはカンガルーケア(STS)の体温上昇作用を検証もしないで、出生直後のカンガルーケアを推奨したが、ザンビアと同様の体温上昇作用が日本の寒い分娩室においてもあるかどうかを早急に検証すべきである。もし、カンガルーケア(STS)に体温上昇作用が認められなければ、分娩直後の赤ちゃんは低体温症に陥り、呼吸循環動態を不安定とし、同時に糖新生を妨げ低血糖症に陥り、心肺停止事故・発達障害児を増やすからである。カンガルーケア(STS)の体温上昇作用の検証には、新生児科医だけでなく、体温の研究に詳しい産科医・麻酔科医・生理学者らも交えた第三者委員会によって行うべきである。 ※ 母乳育児の3点セットとは、 第4条: 母親が出産後30分以内に母乳を飲ませられるように援助する。 (所謂、出産直後のカンガルーケア(STS)を指す) 第6条: 医学的に必要でない限り、新生児には母乳以外の栄養(人工ミルク)や水分を与えないようにする。 (所謂、完全母乳) 第7条: 母子同室にする。母親と赤ちゃんが終日一緒にいられるようにする。 1.出生直後のカンガルーケア (STS) の短所(危険性) 出生直後のカンガルーケア(STS)の短所(危険性)は、①児の全身状態(呼吸・色・筋緊張度)の観察が出来ない、②児の体位が腹臥位 (うつ伏せ寝)のため気道閉鎖(窒息)を起こし易い、③日本の寒い分娩室におけるカンガルーケア(STS)は、出生直後の寒冷刺激に伴う体温下降をさらに強め、下肢の末梢血管及び肺動脈を収縮し、肺高血圧症の病態(呼吸循環動態の不安定)を促進する、④母子同室(低温環境)での長時間のカンガルーケアと完全母乳の組み合わせは、「低体温症⇔低血糖症」の悪循環を形成する。低血糖症を見逃し医学的管理(保温・栄養・酸素)が遅れると、児は重度の低血糖症に陥り、生命維持を司る自律神経は機能を失い筋緊張低下を増す。筋弛緩はうつ伏せ寝の状態で呼吸運動を抑制し、血中の酸素濃度を低下させ、同時に、気道閉鎖(窒息)の危険性を増す。低血糖症が危険な理由は、生命維持を司る自律神経が機能不全に陥るため、呼吸循環器など全ての臓器の調節機能が失われる事である。⑤ケイレン・無呼吸発作などの症状が表に出ない中等度の低血糖症(無症候性低血糖)が長時間持続すると、発達障害(自閉症)を増やす。⑥正常妊婦から生まれた高インシュリン血症の赤ちゃんをカンガルーケア(STS)と完全母乳で管理すると、低血糖症の進行は早く、生後一時間以内に心肺停止を起こす危険性がある。 ※高インシュリン血症児は、妊娠糖尿病の母親からだけでなく、正常妊婦からも高率に生れる。問題は、高インシュリン血症児かどうかの診断が出生前に出来ない事である。高インシュリン血症児は、母乳育児3点セットの短所(低体温症・低血糖症)の犠牲になり、発達障害(自閉症)・心肺停止事故に遭っている可能性が強い。この事は、第24回日本母乳哺育学会(2009年9月:東京)で報告した。 以上の様に、出生直後のカンガルーケア(STS)には、短所(危険性)が多数あるにも係らず、ワーキンググループは、高インシュリン血症児を犠牲にしてまで、なぜ母乳育児3点セットを推奨するのかが分からない。産科医は声を大にしてカンガルーケアの中止を国(厚労省)に訴えるべきである。問題は、日本産婦人科医会がワーキング・グループのガイドラインを推奨している事である。 ⑴ カンガルーケア(STS)は、児の全身状態の観察に不適、 赤ちゃんの全身状態を全く観察できないカンガルーケア(STS)は、以下の三つの理由から即刻止めるべきである。 ①呼吸状態の異常(多呼吸、陥没呼吸、呻吟、鼻翼呼吸、窒息)が外から見えない ②全身色(チアノーゼの有無)が見えない、 ③筋肉の緊張度(低血糖症のサイン)が見えない ※カンガルーケア(STS)の短所 児は母親の胸・腹の上に“うつ伏せ寝”の状態で寝せられ、体はタオルや毛布などで全身を被われているために、児の呼吸運動・全身色(チアノーゼの有無)・筋緊張度(低血糖症の有無)が外から全く見えない。つまり、カンガルーケア(STS)は、児の危険信号(異常)を見落とし、対応(初期治療)が遅れる事が一番の短所である。素人の母親には勿論、プロの助産師が母親の側で児を観察したとしても、児の異常(手足の冷たさ・チアノーゼ・筋緊張低下・無呼吸発作など)に気付くのが遅れる。異常に気付いた時は、児は既に無呼吸(心肺停止)状態に陥った場合が殆どである。たとえ新生児蘇生術を習得した医師がいて、蘇生によって救命できたとしても、脳に永久的な障害を遺す。酸素飽和度モニターで異常(低酸素血症)を見つけ治療(蘇生)するのではなく、異常が起きないようにする為の安全対策 (予防医学)を優先した新生児管理を国は推奨すべきである。 ※事故責任 出生直後の呼吸循環動態が不安定な新生児の管理には、上記3項目は医療従事者に課せられた最低限の注意事項である。すなわち、出生直後のカンガルーケア中・母子同室中に心肺停止などのトラブルを引き起こし、児に永久的な脳障害を遺した事故責任は、上記の危険信号を見落とし、初期治療を遅らせた医療側と、安全対策を無視し、「授乳と離乳の支援ガイド」を推奨した国(厚労省)に責任がある。母親のお腹の上で心肺停止事故があったとしても、母親の管理責任は無い。国は、出生直後の新生児は呼吸循環動態が非常に不安定と公表するならば、新生児管理を医療機器(酸素飽和度モニター)に頼るのではなく、全身状態の観察が可能な人の目による新生児管理法を推奨すべきである。 ⑵ カンガルーケア(STS)中の新生児の体位(うつぶせ寝)の問題点 首がまだ座らない出生直後の赤ちゃんを母親のお腹の上に乗せ、水平位(うつ伏寝)の状態で授乳(直母)をすると、児頭の重さ(体重の約30%)で口が塞がれ、鼻腔も乳房で圧迫され気道閉鎖(窒息死)を招く危険性がある。とくに、帝王切開術後の母親の体位は、ほぼ水平位のため窒息を起こし易い。また、低血糖症の新生児は筋緊張が低下しているため、うつぶせ寝の状態では容易に窒息する。事故例の64%(9/14人)は水平位だったと報告されている。うつぶせ寝の状態では、窒息の危険性があることを予測しなかった医療側の医学以前の初歩的ミスである。 ※カンガルーケア中の母親のポジションの危険性 母親が寝た状態(水平位)での直母は、児の口腔は乳房で塞がれるため赤ちゃんは口呼吸が出来ない。故に、直母は鼻腔が乳房で塞がれない様な体位で行うのが原則である。窒息(気道閉鎖)を防ぐためには、母親は水平位ではなく、座位あるいは立位で、母親の手で児の頭部を支え、鼻腔が乳房で圧迫(窒息)されないように直母(授乳)すべきである。 分娩台や母子同室中のベッドの上で、母親が寝た状態での授乳(直母)は、窒息事故をおこしても何ら不思議ではない。直母(授乳)は母親がベッド上で座った状態で行うべきで、たとえ出産直後の母親が分娩台・ベッド上での長時間のカンガルーケアを希望したとしても、水平位(うつ伏せ寝}でのカンガルーケアは絶対に行うべきでない。母親はお産の疲れでカンガルーケア中に寝てしまい、窒息事故を招く危険性が大きいからである。特に、帝王切開術後の母親は、痛みを取るための鎮痛剤・鎮静剤が注射されている為に寝入ってしまう危険性がある。出産後の母親は、深夜は眠るのが当然であり、深夜、術後患者にカンガルーケアをさせ、赤ちゃんの管理を母親一人に任せるのは無謀すぎる。 ※カンガルーケア中の心肺停止事故は、乳幼児突然死(SIDS/ALTE)ではない。 カンガルーケア中に事故に遭った新生児のカルテには、心肺停止の原因は「原因不明の病気であるSIDSの病態が考えられる」と記載されている。病院側と国は、原因不明とし責任逃れをしたいのであろうが、両者の病態は全く異なる。うつぶせ寝は乳幼児突然死(SIDS/ALTE)の危険因子である事に間違いない。ところが、SIDSは着せ過ぎ・温め過ぎによる高体温症(うつ熱)が原因である。一方、カンガルーケア中の心肺停止は出生直後の寒冷刺激に伴う低体温症(冷え性)が原因である。SIDSは着せ過ぎ(放熱障害)・温め過ぎなどによる高体温症(うつ熱)を防ぐための体温調節機構、つまり、持続的な末梢血管拡張(交感神経抑制)と産熱抑制(筋弛緩=呼吸抑制)が低酸素血症(心肺停止)を引き起こす。 一方、カンガルーケア中の心肺停止のメカニズムは、低体温症を防ぐ為の放熱抑制を目的とした持続的な末梢血管収縮と産熱亢進(筋肉運動⇒糖消費増大⇒低血糖症⇒筋弛緩)が原因である。 SIDSは末梢血管の拡張、カンガルーケア(STS)は末梢血管の収縮、両者には血管の拡張と収縮の違いがある。 “呼吸循環動態”は児が恒温状態の時に安定するが、体温が正常(37℃)であっても、高温環境下で末梢血管が持続的に拡張した場合、低温環境下で末梢血管が持続的に収縮した場合、つまり、交感神経のバランスが崩れた時に呼吸循環動態は不安定となる。出生直後の赤ちゃんの呼吸循環動態を不安定にする理由は、体温調節(放熱抑制)のために末梢血管が持続的に収縮(交感神経優位)しているからである。カンガルーケア中の心肺停止事故は原因不明のSIDSではなく、国と医療側が出生直後の赤ちゃんの低体温症・低血糖症・低酸素血症を防ぐための安全対策を怠ったために発生した医療事故である。 ⑶ カンガルーケア(STS)は、低体温症・低酸素血症・低血糖症を促進(危険度↑) ※ 分娩直後の “寒冷刺激” について 寒冷刺激とは、子宮内の温度(約38℃)と分娩室の温度(24℃~26℃)の環境温度差(約12℃~14℃)を言う。子宮内温度は一定であるので、寒冷刺激の強さは分娩室の室温で決まる。日本の分娩室は出生直後の赤ちゃんではなく、大人に快適な環境温度に設定されている。出生直後の裸の赤ちゃんにとって快適な環境温度は32℃~34℃(中性環境温度)である。ところが、赤ちゃんを管理する大人は、日本の分娩室・母子同室中の母親の部屋が、児に寒過ぎる環境である事を見落としている。出生直後の赤ちゃんの体温(平均38,2℃)が、生後1時間以内に2℃~3℃も低下する理由は、赤ちゃんの体温調節機構が未熟だからではない。分娩室の温度が児に寒過ぎるにもかかわらず、新生児を管理する大人がカンガルーケアを優先し、体温管理(保温)を怠ったからである。 昔の産婆は、「産湯」を沸かし、部屋の温度をあげ、寒冷刺激を少なくして、低体温症を防いでいた。しかし、現代医学を学んだ助産師は、産湯をやめ、寒冷刺激の強い寒い部屋でカンガルーケアを行い、低体温症の赤ちゃんを増やした。この低体温症を防ぐための体温管理(保温)を怠ったことが、児を低酸素血症・低血糖症に落とし入れ、心肺停止・発達障害を引き起こしているのである。現代医学(母乳育児3点セット)は、元気に生れた正常新生児を低体温症の犠牲にしているのである。 ※ 出生直後の赤ちゃんは、一時的に “低体温ショック” の状態 教科書では、出生直後の2℃~3℃の体温低下を “生理的体温下降”と記載されているが、臨床的には一過性の “低体温ショック”の状態と見なすべきである。何故ならば、出生直後の児の中枢(胸部)と末梢(足底部)の深部体温較差が大きく、足底部の末梢深部体温は30℃以下つまり出生時から8℃以上も低下するからである。大人が“低体温ショック”に陥れば、腸の機能(蠕動運動・消化・吸収・排出)が一時的にストップする様に、出生直後の新生児の消化管機能(蠕動運動)も大人と同じである。 新生児早期にしばしば見られる“初期嘔吐”は生理的現象と考えられているが、出生直後の赤ちゃんを生後2~3分以内に32℃~34℃に温められた保育器内収容すると、生理的と考えられていた初期嘔吐はなくなるのである。つまり、初期嘔吐は生理的現象ではなく、寒冷刺激(低体温症)による病的現象(疾病)と考えるべきである。この様に、出生直後の一時的な低体温ショックは、消化管の循環血流を減らし消化管機能(蠕動運動)を低下させると同時に、全ての臓器の循環血流量を減少し、各臓器の機能障害(合併症)を引き起こす。低体温ショックの状態(中枢と末梢深部体温の離開)が一過性のものであれば問題ないが、寒い部屋(分娩室・母子同室)で体温管理(保温)を怠るならば、中枢と末梢深部体温の離開は進み、末梢血管は収縮を強め、呼吸循環動態・血糖値を不安定とするのである。 中枢と末梢深部体温の離開とは、末梢深部体温の低下つまり末梢血管が収縮して、手足が冷たい “冷え性”の状態である。ところが、出生直後からの児の体温下降を1℃前後に抑える工夫(保育器内収容)をすれば、自律神経機能は正常に保たれ、呼吸循環動態や血糖値は安定し、カンガルーケア中の心肺停止事故・発達障害児は予防できるのである。即ち、出生直後の赤ちゃんの呼吸循環動態を安定化させるためには、出生直後の体温下降を最小限に留め、恒温状態への移行を早める工夫をすることが必要である。赤ちゃんの手足が冷たくなる様な寒い部屋で、体温管理(保温)を無視したカンガルーケア(STS)は絶対に行うべきでない。 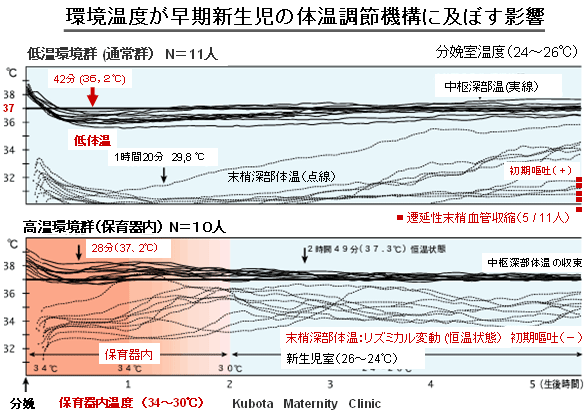 ※現代医学の間違いは、寒冷刺激によって生じた適応障害を安易に生理的現象で済ましている事である。例えば、生理的体温下降、生理的低血糖、生理的初期嘔吐、生理的黄疸、生理的体重減少などは、すべて生理的現象で片付けられている。その為に、新生児の低体温症・低血糖症・嘔吐・重症黄疸・体重減少(低栄養・脱水)の予防法に関する医学的研究は全く進んでいない。国は生後間もない赤ちゃんの呼吸循環動態は不安定と発表したが、出生直後の寒冷刺激を少なくする工夫(保育器内収容)によって、持続的な末梢血管収縮(冷え症)はなくなり、より早く恒温状態に移行させることによって新生児の呼吸循環動態・糖代謝は安定し、ヒヤリハット事例・心肺停止事故・発達障害(自閉症)を防止する事が出来るのである。 ■カンガルーケア(STS)は、チアノーゼ(低酸素血症)をなぜ増強するのか 国の報告によると、出生直後の赤ちゃんは呼吸循環動態が不安定と決め付けつけているが、不安定の理由は、赤ちゃんに原因があるのではなく、出生直後の寒冷刺激が強すぎたために肺血管収縮が強くなり、肺高血圧症の病態を招いたからである。出生直後の寒冷刺激によって肺血管収縮が強くなると、心臓(右心室)から肺動脈に駆出された血液は、肺をバイパスし、胎児期の動脈菅・卵円孔を経由して大動脈に直接流入する。つまり、出生直後の寒冷刺激が強すぎると、下肢の末梢血管収縮に連動し肺動脈血管も収縮するため、肺血管抵抗が増強する。その結果、肺を循環する血流量は減少するため、肺でのガス交換率は低下する。事故に遭った赤ちゃんは、心肺停止の前にチアノーゼが出ているが、ガス交換(酸素化)されていない血液が血中に増えたからである。チアノーゼが強くなると血中の酸素濃度は減少し、やがて心肺停止に至る。周産期シンポジウム2010によれば、カンガルーケア(STS)中に、児の状態の悪化などでSTSを中断した理由で最も多かったのは、チアノーゼの増強、低体温、低酸素、無呼吸と報告されている。これらの症状は、まさに肺高血圧症の存在を裏付ける決定的な証拠である。 出生直後の新生児に下記の症状が認められれば、先ず “肺高血圧症” を一番に疑うべきである。また、これらの症状(チアノーゼの増強、低体温)は、カンガルーケア中の心肺停止事故はSIDS(ALTE)ではない事を裏付けるものである。SIDSは、顔色はピンク、高体温(うつ熱)、発汗、そして心肺停止後も体に温もりがある事が疫学調査で分かっているからである。 ところで、出生直後の軽度のチアノーゼは、初期嘔吐や新生児黄疸と同じ様に出て当たり前の様に思われているが、寒冷刺激を少なくする体温管理つまり32℃~34℃に温められた保育器内に収容するだけでチアノーゼ(低酸素血症)は出なくなる。出生直後の赤ちゃんを生後2~3分以内に保育器内に収容すると、末梢深部体温(足底部の体温)は保育器内の設定温度(32℃~34℃)以下に下降する事はなく、冷え性(末梢血管収縮)を未然に防ぎ、体温をより早く恒温状態に安定させる事によって、肺高血圧症(チアノーゼ)の発症を未然に防止するのである。新生児は、最初に暴露された環境温度に応じて、体外生活への異なった体温の適応過程を示すことが科学的に証明されている。出生直後の赤ちゃんを如何に早く恒温状態に安定させ得るかが、赤ちゃんを事故から守る医療従事者に課せられた究極のテーマなのである。 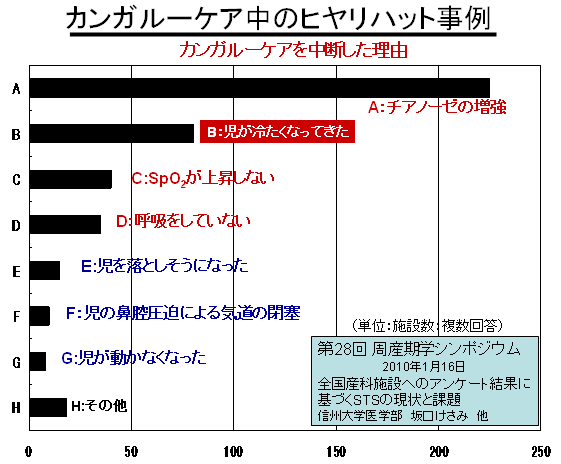 世界の全ての助産師が母乳育児3点セットを見直し、新生児の冷え性を防ぐ体温管理(保育器内収容)と生後数日間の飢餓状態(低血糖)を防ぐ予防医学(安全対策)を導入したならば、発達障害(自閉症)・心肺停止事故は激減すると断言する。厚労省は予防医学の重要性を日本だけではなく、世界に向けて発信し、世界平和に貢献すべきである。 ■カンガルーケア(STS)は、低血糖症を何故増強するのか 寒冷刺激を受けた赤ちゃんは出生直後の体温下降(低体温症)を防ぐために、放熱抑制(末梢血管収縮)と産熱亢進(筋肉運動=啼泣)の二つの体温調節機構を同時に作動し、体温を正常(恒温状態)に維持しようとする。体温調節において、赤ちゃんと大人の違いは、寒いときには大人は震えて体温を上げるが、赤ちゃんは震えない代わりに泣いて(啼泣=筋肉運動)体温を上げる。 ところで、日本の分娩室は赤ちゃんの体温調節機構の能力を超えて寒過ぎるため体温管理(保温)を怠ると、赤ちゃんは容易に「低体温症⇔低体温症」の悪循環に陥る。低体温症が児に不利益な点は、赤ちゃんは未だ母乳(カロリー)摂取が出来ていないにもかかわらず、自律神経の働きで放熱抑制・産熱亢進の二つの体温調節機構が自動的に作動するからである。つまり、赤ちゃんは放熱を防ぐために末梢血管を収縮し、さらに熱産生を増やす為に全身の筋肉運動(啼泣)によって体温を上げようとする。その結果、赤ちゃんは血中の限られたエネルギー(糖分)を消費してしまう。生後10~12時間前後でエネルギー(糖分)は枯渇すると報告されているが、熱産生(筋肉運動)に大量の血中グルコースが消費されるからである。分娩直後から母乳が十分に出るのであれば問題ないが、生後24時間以内では母乳は滲む程度しか出ていない。つまり、出生当日の赤ちゃんは真に飢餓状態にある。心肺停止事故が生後12時間以内に多発する理由は、熱産生に要するエネルギー(糖分)消費が多いにもかかわらず、赤ちゃんが生きる為に必要な最低限のカロリー(基礎代謝量)を飲ませていないからである。以上の理由から、※寒い部屋で母乳以外の栄養(人工ミルク)を与えなければ、児は容易に低血糖症・低栄養状態(飢餓)に陥る。また、低温環境下で末梢血管が収縮した状態、つまり冷え症の状態が長時間に及ぶと、肝臓・腎臓における糖新生が抑制され、医学的管理(保温+栄養+酸素)を怠れば低血糖症はさらに重症化するのである。 ※高インシュリン血症児は、母乳育児3点セットの犠牲に 重度の高インシュリン血症の赤ちゃんを、母乳育児3点セット(カンガルーケア+低温環境+完全母乳)で保育管理したならば,「低体温症⇔低血糖症」の悪循環は避けられない。問題は、分娩前に高インシュリン血症児であるかどうかの診断が出来ないことである。高インシュリン血症児は、母乳育児3点セットの犠牲になっている事は間違いない。事実、生後15分後の血糖検査で重度の低血糖症(28mg/dl)と診断されたにもかかわらず、その後カンガルーケアを行い、約30分後に心肺停止となり、その後、脳性麻痺と診断された事例がある。高インシュリン血症児は、心肺停止がいつ起こっても不思議ではない。分娩前に高インシュリン血症児であるかどうかの診断がつかない現状においては、母乳育児3点セットのデメリットは大き過ぎる。完全母乳、出生直後のカンガルーケアの危険性については、厚労省の「授乳と離乳の支援ガイド」研究班、日本母乳哺育学会などに報告済みである。 2.カンガルーケア(STS)の長所 “体温上昇作用” に科学的根拠なし ※日本周産期・新生児医学会と日本産婦人科医会の発表に異議! 新生児科医からなるカンガルーケア・ガイドラインワーキンググループは、出生直後のカンガルーケア(STS)には、⑴体温上昇作用、⑵血糖値の安定、⑶呼吸循環の安定などの利点があると報告した。グループの一人である渡部医師(新生児科医)は、外国論文(ザンビア)の臨床データを引用し、カンガルーケアの体温保持作用について、「児の体温は保育器に収容するよりもカンガルーケアの方がより早く上昇し安定化する」を日本周産期・新生児医学界誌(第47巻、第4号2011年12月)に発表した。また、日本産婦人科医会幹事の鈴木俊治医師(葛飾赤十字産院院長)も渡部医師と同じ外国論文(Christensson 1998)を引用し、新生児の体温は保育器よりもカンガルーケアのほうが早く安定化すると第50回記者懇談会(2012年1月18日)で報告している。下図 |
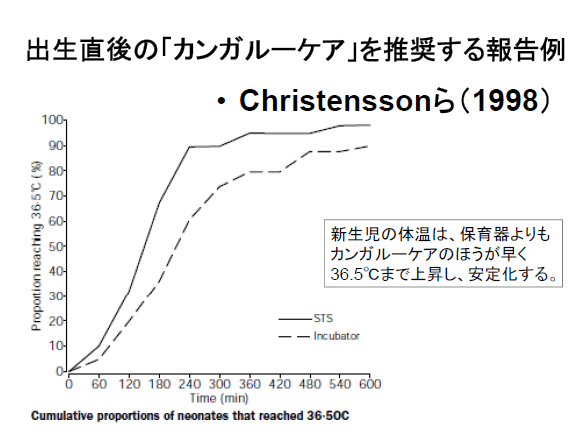 日本周産期・新生児医学会と日本産婦人科医会は、赤ちゃんが低体温症や手足が冷たくなった時は保育器に入れて治療するよりも、カンガルーケア(STS)で母親の体温で温めた方がより早く正常体温(恒温状態)に安定する。つまり、両学会は低体温症の赤ちゃんは保育器に入れる今迄の医療よりも、カンガルーケア(STS)で温めた方がより良い結果が出ると、医療現場に誤解を招く内容を発表した。医学的常識を覆す両学会の今回の発表は、医療従事者(特に助産師)がカンガルーケアの体温上昇作用を信じ、冷たくなった赤ちゃんを保育器ではなくカンガルーケア(STS)を選択する事態が起こり得る。事実、新生児室で生後10時間目の赤ちゃんの手足が冷たくなり、冷たくなった赤ちゃんを助産師が母親の所に連れてきて、「手足が冷たいから抱っこして温めてください」、と言い残して助産師は部屋を出ていき、その後の観察もなかった。児は1時間後に心肺停止状態で見つかった。児は、一命は取り留めたが、現在、脳性麻痺の状態で、意識が無いまま人工的に呼吸管理されている。赤ちゃんに優しい病院(BFH)に認定された病院での出来事である。 ⑴カンガルーケア(STS) の “体温上昇作用”に、科学的根拠なし 日本の寒い分娩室においても、出生直後のカンガルーケア(STS) に “体温上昇作用”があるならば、「血糖値の安定化」・「呼吸循環の安定化」は信頼できる。しかし、出産直後のカンガルーケアに体温上昇作用がなければ、血糖値の安定化・呼吸循環器の安定化はあり得ない。日本周産期・新生児医学会および日本産婦人科医会は、日本の寒い分娩室においても出生直後のカンガルーケア(STS)にザンビアの臨床データと同様の体温上昇作用があるかどうかを検証すべきである。カンガルーケア(STS)で事故が多発する理由は、ワーキンググループが日本の寒い分娩室で体温上昇作用を確認もせず、⑴体温上昇作用、⑵血糖値の安定、⑶呼吸循環の安定、などの利点があると発表したからである。 ⑵ザンビア(後発開発途上国=最貧国)の臨床データの問題点 渡部医師・鈴木医師が引用した外国論文は、日本の寒い分娩室における正常成熟児の出生直後からのカンガルーケアのデータではなく、ザンビア(南アフリカ)の臨床データを引用しての報告であるところに問題がある。しかも、調査研究の対象は、正常成熟児の出生直後からのカンガルーケアのデータではなく、主に早産児(平均33週~34週)、低出生体重児(平均1890g~2183g)であり、入院時の児の平均体温(直腸温)は34℃であったと記録されている。日本(先進国)の周産期医療の臨床現場に、後発開発途上国(ザンビア)における早産児、低出生体重児の臨床成績をなぜ参考文献として引用するのかが問題である。(尚、後発開発途上国とは、開発途上国の中でも特に開発が遅れている国の事を云う。) 3.NICUでのカンガルーケアはなぜ安全か 出産直後のカンガルーケア(STS)中に心肺停止事故が多く、NICUでのカンガルーケアに事故が発生していない。その理由について述べる。 ◆NICUでのカンガルーケアが安全な理由 ① NICUでは、母親は座位でカンガルーケアを行うために窒息事故は防げるが、出生直後のカンガルーケア(STS)は母親の体位が分娩台・ベッド上で水平位のため、お腹の上に乗せられた赤ちゃんは「うつぶせ寝」の状態となり、口腔・鼻腔は塞がれ、解剖学的に気道閉鎖(窒息死)を起こし易い。 ②NICU入院中の新生児には出生直後の寒冷刺激(胎内と胎外の環境温度差)が無いために、児は恒温状態に安定している、すなわち、呼吸循環・消化管・糖代謝などを司る自律神経機能は正常に保たれている。一方、出生直後の赤ちゃんは、低体温症、冷え性の状態で末梢血管は収縮し、自律神経は交感神経優位(カテコラミン↑)に偏り、呼吸循環動態・糖代謝を不安定としている。③ NICU入院児は、新生児が1日に必要とする基礎代謝量(50kcal/kg/day)以上のカロリーを摂取している。つまり、NICU入院児は飢餓状態ではない。また、NICUは赤ちゃんに快適な環境温度に調節されているため自律神経機能は安定し、低体温・低血糖に陥る危険性が無い。 一方、寒い部屋(分娩室・母子同室)でのカンガルーケアと完全母乳の赤ちゃんは、生後24時間以内は飢餓状態にある。また、手足が冷たい冷え性(末梢血管収縮)の赤ちゃんは、肝臓・腎臓での糖新生が抑制され、消化管機能(消化・吸収)も低下しているため低血糖症に陥り易い。故に、医学的管理(体温管理+栄養管理)を怠ると、低血糖症は進み、チアノーゼ・ケイレン・筋弛緩・無呼吸発作などのヒヤリハット事例を招く。低血糖症が遷延すると発達障害(自閉症)児を増やす。発達障害の原因が不明と診断される理由は、ただ血糖検査を行っていないからである。(※ガイドラインは、カンガルーケア(STS)中の酸素飽和度モニターの使用を義務付けているが、末梢深部体温(冷え症)・血糖値のモニターは酸素飽和度モニター以上に重要である。カンガルーケア中の酸素飽和度の低下は、低体温(冷え性)・低血糖が引き金となり発症した結果であるからである。 ④NICUは、大人ではなく赤ちゃんに快適な環境温度に設定されている。一方、分娩室や母子同室の母親がいる室温は、赤ちゃんではなく、大人に快適な環境温度に設定されている。つまり、NICUの室温は分娩室より温かい環境温度に設定されている為に、栄養が確立したNICU入院児は余程のアクシデントが無い限り、低体温症・低血糖症に陥ることはない。NICUが安全な理由は、低体温症・低血糖症の赤ちゃんがいないからである。 ⑤分娩室には助産師がいるが、助産師はお産のプロであって、新生児管理のプロではない。NICUには、新生児の体温・栄養・呼吸循環などの全身管理を専門とする看護師が赤ちゃんを24時間体制で観察しているので安全である ⑥助産師は出生直後のカンガルーケア・完全母乳・母子同室の長所を学習しているが、短所(低体温症・低血糖症の危険性)についての学習は殆んどしていない。その証拠に、産後の子宮収縮の目的で母親の下腹部にアイスノンをのせ、その母親にカンガルーケアを行い、心肺停止事故を起こした事例が複数ある。アイスノンが赤ちゃんに危険な理由は、下肢の末梢血管収縮を強め、下肢から心臓に戻る静脈還流を減少させ、血圧低下を招くことである。同時に、アイスノンは下肢の末梢血管収縮と連動し肺血管も収縮するため、低血圧も手伝って、肺高血圧症(チアノーゼ)の病態(呼吸循環動態の不安定)を引き起こすからである。下図 |
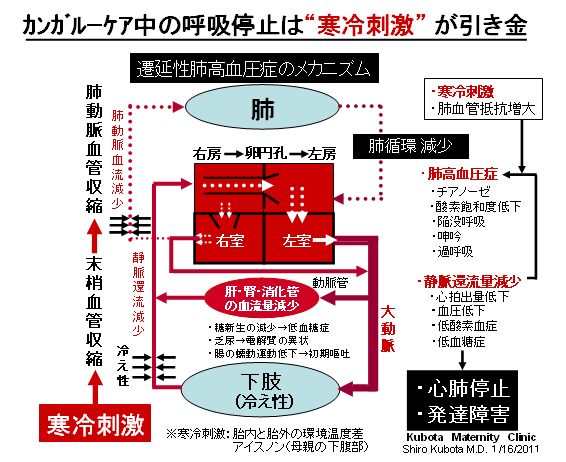 ※下肢が冷えると何故危険か、保温がなぜ重要か、日本の助産師は母乳育児を学習する前に、新生児の低体温症・低血糖症・低栄養(飢餓)の危険性を学ぶべきである。産直後の母親の下腹部にアイスノンをのせたり、赤ちゃんは “3日分の水筒と弁当” を持って生れてくる、科学的根拠の無いこの俗説を信じた助産師が大勢いる限り、赤ちゃんは「冷え」と「飢餓」に苦しみ、低体温・低血糖・低栄養(飢餓)による事故を繰返す。NICUが安全な理由は、NICUのナースは科学的根拠の無い精神論より、科学的根拠に基いた医療を優先するからである。一方、助産師は科学より自然主義と精神論を優先するところに両者の違いがある。科学が育たない所に事故が増えるのは当たり前である。 ※NICUのカンガルーケアが安全な理由は、新生児管理の基本である体温管理・栄養管理・呼吸管理が、新生児の全身管理を専門とするスタッフによって管理されているからである。一方、出生直後のカンガルーケア(STS)が危険な理由は、分娩室・母子同室の部屋が児にとって寒すぎるにもかかわらず児の体温管理(低体温予防)を怠り、さらに母乳が出ていないにもかかわらず栄養管理(低血糖予防)を怠り、赤ちゃんを低体温症・低血糖症(低栄養)・低酸素血症から守るための安全対策(予防医学)を怠っているからである。日本では産科医不足のため院内助産院が増える傾向にあるが、赤ちゃんにとって危険が多すぎる。厚労省は院内助産院の長所だけでなく、短所(予防医学の欠如)についても知るべきである。 4.出生直後の新生児の体温調節機構(放熱抑制+産熱亢進)の特長 ⑴放熱抑制=末梢血管収縮(カテコラミン↑)⇒手足が冷たい(所謂、冷え性) ・末梢血管収縮⇒ 肺血管収縮 ⇒ 肺高血圧症⇒チアノーゼ(低酸素血症↑) ・末梢血管収縮⇒静脈還流↓⇒低血圧⇒肝血流量↓⇒糖新生↓⇒低血糖症 ・末梢血管収縮⇒消化管血流↓⇒腸運動↓⇒嘔吐↑⇒哺乳障害⇒低血糖症 ⑵産熱亢進=筋肉運動(啼泣=産声) ・啼泣(全身運動)⇒産熱亢進⇒酸素消費↑+グルコース消費量↑⇒低血糖症 ※体温調節のメカニズム 寒冷刺激を受けた出生直後の赤ちゃんは、低体温症から己を守るための体温調節機構(放熱抑制+産熱亢進)を作動させ、正常体温[恒温状態]に安定しようと努力する。すなわち、⑴放熱抑制と⑵産熱亢進は、体温を正常(恒温状態)に保つ為の恒温動物にとって不可欠な体温調節機構である。ところが、出産直後の寒冷刺激が強過ぎた場合、体温管理(保温)を怠り低体温症が長引いた場合、この体温調節機構(放熱抑制+産熱亢進)は、上記のメカニズムによって生命維持に最も危険な低酸素血症(肺高血圧症)と低血糖症を誘発する。生命維持を司る自律神経機能は、呼吸循環・糖代謝などの調節(安定化)よりも、体温を正常(37℃)に保つための体温調節機構(放熱抑制+産熱亢進)を優先して作動する。※カンガルーケア中の心肺停止の原因が分からない理由は、心肺停止 の原因が病気によるものではなく、低体温症を防ぐための体温調節機構が二次的に低酸素血症と低血糖症を引き起こしているからである。低体温症を防ぐための体温調節機構、つまり、恒温動物がもつ生理学的な自己防衛反応が低酸素血症・低血糖症を誘発して、心肺停止事故を引き起こしているのである。 ※低血糖症は発達障害(自閉症)の危険因子 寒い部屋で体温管理を怠りガルーケア(STS)を長時間すると、児は低体温症(冷え性)に陥り、「低体温症⇔低血糖症」の悪循環を促進する。低体温・低血糖を防ぐための医学的管理(保温+カロリー補給+酸素)を怠り、母乳以外の栄養(糖水や人工ミルク)を与えなければ、出生直後の一過性の低血糖症は中等度から重度の低血糖症に陥る危険性を増す。特に、高インシュリン血症児をカンガルーケア(STS)と完全母乳で保育管理すると、重度の低血糖症に陥る危険性が高い。中等度の低血糖症が持続すれば、無呼吸発作・ケイレンなどの症状が表に表れなくても、脳に永久的な障害(発達障害)を遺す危険性がある。日本では厚労省が母乳育児推進運動を始めたのを契機に、発達障害児(自閉症)が驚異的に増加しているが、増加の理由は、医療従事者が低体温症・低血糖症を防ぐための安全対策を怠り、症状が表に出ない無症候性低血糖症(中等度の低血糖症)を増やしていることが一因と考えられる。 5.根拠と総意に基づく、カンガルーケア・ガイドラインの問題点 カンガルーケア・ガイドライン ワーキンググループは、出生直後の新生児は正常産であっても呼吸・循環ともに非常に不安定な時期にあることから、カンガルーケアを行うに当たって下記のガイドラインを推奨すると発表した。 健康な正期産児には、①ご家族に対する充分な事前説明、②機械を用いたモニタリング、③新生児蘇生に熟練した医療者による観察、など安全性を確保した上で、出生後できるだけ早期にできるだけ長く、ご家族(特に母親)とカンガルーケアを実施することが薦められる。出生後30分以内から、出生後少なくとも最初の2時間、または最初の授乳が終わるまで、カンガルーケアを続ける支援をすることが望まれます。(根拠と総意に基づくカンガルーケア・ガイドライン(カンガルーケア・ガイドライン ワーキンググループ編、メディカ出版、2009年11月25日発行、p25)より引用) ⑴ 事前説明は、カンガルーケアの短所 (危険性) も説明すべき カンガルーケア・ガイドラインワーキンググループは、ご家族に対する充分な事前説明をする事が重要とガイドラインに掲げているが、カンガルーケアの長所のみならず、短所(危険性)についても詳細に説明すべきである。 カンガルーケア・母子同室中の心肺停止事故が繰返されるのは、カンガルーケアの短所の説明不足と心肺停止の原因を不明とし、乳幼児突然死(SIDS/ALTE)の疑いで誤魔化しているからである。NICUでのカンガルーケアがなぜ安全か、出産直後のカンガルーケア(STS)中に何故事故が多く発生するのか、両者の相違点を事前に説明すべきである。寒い分娩室で出生直後に約13℃の寒冷刺激を受け、臍帯切断によって母親からの栄養(糖分)と酸素が突然に途絶えた赤ちゃんと、NICU入院中の赤ちゃんとでは、寒冷刺激の有無・環境温度・児の栄養状態は全く異なる。事前説明には、両者の相違点を説明すべきである。 ⑵ 機械を用いたモニタリングの問題点 カンガルーケア(STS)中に酸素飽和度モニターで異常が見つかった時は、児はすでに何らかのトラブルが発生した後である。児の全身状態をより早く、より正確にモニターする最善の方法は、児の呼吸状態、色(チアノーゼの有無)、筋肉の緊張度などを、目で観察する方がより早く、より確実である。産科医・助産師・看護師・母親の複数の目で児の呼吸状態・手足の動き・全身色(チアノーゼの有無)などを注意深く観察することは、いかに高価で精巧なモニターを装着するより、より早く児の全身状態の良・不良を確実に評価できる。臨床医学の原点は、検査(モニター)に頼るのではなく、呼吸循環動態が不安定な早期新生児の呼吸状態・児の行動・全身色などを密に観察し、また冷え症の有無をテェック(手足に触る事)する事が最も重要である。児に酸素飽和度モニターを装着し、全身状態が何も見えないカンガルーケアを実施するよりも、寒冷刺激を受けた赤ちゃんをより早く快適な環境温度(保育器内:32~34℃)に収容し、さらに肺呼吸が確立しチアノーゼが消失するまでの約30分間、保育器内に酸素を流し低酸素血症を防ぐ方法は、児の全身管理に優れているだけでなく、児に不利益な低体温症・低酸素血症・低血糖症を未然に防ぐ事が可能である。カンガルーケア中の心肺停止事故は予防医学(安全対策)の導入によって、未然に回避する事が可能である。事故が発生して低体温症・低酸素血症・低血糖症の治療をするよりも、発症する前にそれらの予防を行うべきである。肺高血圧症(チアノーゼ)、無呼吸(低血糖症)が一端発生すると治療は難しく、助かっても脳に障害を遺すのがほとんどである。事故直後に脳の低体温療法を始めたとしても、脳障害が治るものではない。母親が母乳育児(3点セット)の短所(危険性)を事前説明で知ったならば、あえて危険(低酸素血症・低血糖症)をおかしてまで出生直後からの長時間のカンガルーケアを希望する母親はいない筈である。 ⑶ 新生児蘇生に熟練した医療者による観察よりも、事故防止策を最優先すべき 分娩に携わる全ての医療従事者が、新生児の無呼吸発作・心肺停止などの非常事態に備え、蘇生術を学ぶ事は医師として当然である。カンガルーケアを推進する新生児科医は心肺停止の原因は何か、心肺停止事故をいかにして防ぐかを研究・学習することは、ガイドラインを作成し産科医・助産師に蘇生術を学ばせるよりもっと重要である。蘇生術によって一命は取り留めても、脳に障害を遺すケースが多いからである。ガイドライン ワーキンググループは蘇生の前に事故原因を究明し、赤ちゃんの心肺停止事故を防ぐ安全対策(予防医学)を講じるべきである。ワーキンググループに赤ちゃんを事故から守る予防医学の発想があれば、新生児蘇生は回避できるのである。カンガルーケア中に事故が繰返されているにもかかわらず、蘇生を必要とする危険な新生児管理(母乳育児3点セット)を国はなぜ推奨するのか、予防医学を重んじる厚労省は、周産期医療に赤ちゃんを事故から守る安全対策(予防医学)を早急に取り入れるべきである。※呼吸循環動態が不安定で、母乳を飲めない赤ちゃんに、低体温症・低酸素血症・低血糖症を促進するような “ストレステスト”を行うべきではない。 ※カンガルーケア・ガイドライン ワーキンググループ(新生児科医)の問題点 ワーキンググループはカンガルーケアを積極的に推進する新生児科医だけで構成されている所に問題がある。新生児科医は低出生体重児の体温管理、栄養管理、呼吸管理、そして新生児疾患に対する診断・治療のプロであるが、正常新生児が出生直後に低体温症、低血糖症、低栄養(飢餓状態)に陥らないための医療(予防医学)を専門とする医師ではないからである。新生児医療は予防医学が全てと言われるが、予防医学が必要な理由は、出生直後の新生児が肺高血圧症(低酸素血症)・低血糖症・飢餓状態(高Na血症性脱水)に陥った場合、児は脳に何らかの障害を遺す危険性があるからである。出産直後の寒冷刺激に伴う末梢血管収縮(放熱抑制機構)は、新生児にとって最も危険な肺高血圧症(呼吸循環障害)・低血糖症(筋緊張低下)を誘発するが、正常新生児を知らない新生児科医は寒冷刺激の危険性を全く理解していない。 出生直後から児を快適な保育器(中性環境温度:32℃~34℃)に収容すると、児は恒温状態により早く安定し、低体温症に合併する適応障害(呼吸循環動態の不安定)を防ぐ事が出来る。しかし,寒い分娩室でカンガルーケア(STS)を長時間実施すると、赤ちゃんは放熱を防ぐために末梢血管を持続的に収縮し、二次的に肺高血圧症・低血糖症を合併する。カンガルーケア中・母子同室中に心肺停止事故に遭った赤ちゃんの手足が冷たい理由は、寒い部屋で、児は放熱を防ぐ為に手足の末梢血管を持続的に収縮しているからである。 新生児科医は低出生体重児の全身管理(体温・栄養・呼吸)、とくに低体温症の予防には厳重である。しかし、出産直後からの正常成熟新生児のカンガルーケア(STS)を積極的に推進する新生児科医は、分娩室での寒冷刺激(胎内と胎外の環境温度差)が児の体温調節機構・呼吸循環機能・消化管機能・肝腎機能・糖代謝に、どの様な悪影響を及ぼすのかについての知識が不足している。新生児科医は未熟児医療や先天異常、種々の疾病に対する診断学と治療学の専門家であるが、正常成熟新生児の出生直後の低体温症に合併する適応障害(例えば、低血糖症、肺高血圧症、初期嘔吐、低栄養、脱水、重症黄疸、胎便性イレウスなど)から赤ちゃんを守るための予防医学(安全対策)は持ち合わせていない。 産科医は赤ちゃんが病気にならない様に予防医学を取り入れようと工夫するが、母乳育児を推進する新生児科医は出生直後のカンガルーケア・完全母乳・母子同室の重要性は訴えても、赤ちゃんを病気や事故から守る予防医学(安全対策)の重要性を訴える発想は未だ持ち合わせていない。カンガルーケア・ガイドライン ワーキンググループの問題点は、メンバーがカンガルーケアを推進する新生児科医だけで構成され、正常成熟新生児の全身管理(低体温症の予防・低酸素血症の予防・低血糖症の予防)に詳しい産科医が一人も加わっていない事である。つまり、カンガルーケア・ガイドラインは根拠と総意に基づくとあるが、カンガルーケアの長所(体温保持作用)は科学的根拠に乏しく、日本の寒い分娩室における正常成熟新生児のデータではない。以上の理由からガイドラインは根拠と総意に基づいた信頼できる内容ではない。 6.日本産婦人科医会の問題点 ■日産婦医会報 (平成24年2月1日)引用 昨今、出生直後に行うカンガルーケア(early skin to skin contact:STS)中に新生児が呼吸あるいは心肺停止となり、新生児死亡あるいは神経学的後遺症が懸念される報告が続いている。これらの多くはカンガルーケアそのものが原因ではないが、カンガルーケアの実施方法や実施中のモニタリング等に問題があったことが指摘されている。これらを鑑みて、医会ではホームページおよび医会報1月号に出生直後におこなうカンガルーケア実施上の注意事項を掲載した。その経緯等について鈴木敏治母子保健担当幹事が出生直後に行う「カンガルーケア」についてと題して、第50回記者懇談会(平成24年1月18日)で発表した。※出生直後のカンガルーケアにおける注意事項(日本産婦人科医会HPより) 1.適応基準・除外基準等を含めて、「カンガルーケア・ガイドライン」(カンガルーケア・ガイドラインワーキンググループ編、等を参考にした施設ごとの実施マニュアルを作成する。 2.母親(および家族)に対して、新生児の顔色や呼吸等の観察の重要性および新生児のポジショニング等を含めた十分な事前説明を行い、母親(および家族)が「カンガルーケア」を理解し希望していることを確認した上で実施する。 3.母親(および家族)が新生児の観察を自力のみで行うことには限界があるため、必ず医療側も十分な観察を行う。 4.「カンガルーケア」実施に携わる医療者は新生児蘇生に熟練している必要がある。 ※日本産婦人科医会は、新生児科医だけによるカンガルーケア・ガイドラインワーキンググループが編集した「カンガルーケア・ガイドライン」を参考にして施設ごとの実施マニュアルを作成するように会員に注意を促しているが、ガイドラインワーキンググループが作成したガイドラインは、根拠と総意に基づいた信頼性のある内容ではない。何故ならば、ワーキンググループのメンバーに正常成熟新生児の出生直後の体温管理・栄養管理を専門とする産科医が一人も入っていないからである。 ①新生児科医と産科医の違いは先に述べたが、新生児科医は低出生体重児などのハイリスク児の低体温症・低血糖症の予防には厳重な注意を払うが、出生直後のカンガルーケアを積極的に推進する新生児科医は、早期新生児の低体温症・低血糖症を防ぐための安全対策(予防医学)を見落としている。※分娩直後の寒冷刺激(胎内と胎外の環境温度差)が正常成熟新生児の体温調節機構に及ぼす影響、つまり、放熱抑制を目的とした末梢血管収縮・熱産生を目的とした筋肉運動(啼泣)が児の呼吸循環動態・消化管機能・肝腎機能・糖代謝などに、どの様な悪影響を及ぼすのかについての知識が不足している。日本産婦人科医会は、「カンガルーケア・ガイドライン」を参考にする様にと産科医に指導したが、元気に出生した赤ちゃんにとって、産科医にとって、余りにも無責任な指導である。出生直後の「カンガルーケア・ガイドライン」は異常児を専門とする新生児科医ではなく、正常成熟児の管理を専門とする日本産婦人科医会が中心となって、赤ちゃんを事故から守る安全対策を考慮したガイドラインを作成すべきである。 ②日本産婦人科医会の問題点として、同会の鈴木母子保健担当幹事は南アフリカのザンビア(後発開発途上国=最貧国)の臨床データを引用し、カンガルーケア(STS)は保育器よりも体温上昇作用の効果があると、日本産婦人科医会のホームページに報告している。鈴木医師の発表を刷り込まれた医療従事者は、出生直後の低体温症の赤ちゃんを本来なら保育器に収容すべき所を、カンガルーケア(母親のお腹の上)で温めようとする助産師が増えてくる危険性がある。事実、手足が冷たくなった赤ちゃんを助産師が新生児室からわざわざ母親のいる部屋に連れてきて、カンガルーケアで体を温めて下さい、と言って母親に管理させ、約1時間後に心肺停止事故を起こした事例がある。日本産婦人科医会は鈴木医師が引用したザンビアのデータが真実かどうかを早急に検証し、事実と異なるならば間違いを改め、会員だけでなく国民にも公表・報道すべきである。国は、出生直後の新生児の呼吸循環動態は不安定と決め付け、心肺停止の原因は不明とし責任逃れをしているが、真実は、低体温症の予防を怠り、呼吸循環動態・血糖値を不安定にし、心肺停止事故を繰り返しているのである。 鈴木母子保健担当幹事は、出生直後の「カンガルーケア」を推奨する報告例の中で、新生児の啼泣について、次の様に述べている。(疼痛刺激や空腹などによらない)出生後の新生児の啼泣は、元気さの指標でなく、母子分離の不安によるもので、母親に直接抱かれることによって軽減する。鈴木医師は出生直後のカンガルーケア(母親に直接抱かせること)のメリットを訴えたいのであろうが、出生直後の新生児が泣く理由は、母子分離の不安によるのではなく、新生児が低体温症を防ぐための体温調節機構の働きによる行動であることを強調する。出生直後の新生児の行動(啼泣・睡眠・覚醒など)は、母子分離の感情に左右されるのではなく、低体温症を防ぎ恒温状態に移行するための体温調節機構の働きそのものである。 日本産婦人科医会の母子保健担当幹事が、南アフリカのザンビア(後発開発途上国)の臨床データを引用し、カンガルーケア(STS)は保育器よりも体温上昇作用の効果がある、さらに、「出生後の新生児の啼泣は、元気さの指標でなく、母子分離の不安によるもので」、等の科学的根拠のない論文を何故引用し発表したのか、日本産婦人科医会の信用は“ガタ落ち”と云わざるを得ない。「カンガルーケア(STS)は保育器よりも体温上昇作用の効果がある」を発表した日本産婦人科医会は、日本の寒い分娩室においてもザンビアのデータと同じ体温上昇作用の効果があるかを早急に検証し、その結果を医会報・記者懇談会で公表すべきである。 ◆母親が出産後 “30分以内”に母乳を飲ませられるように援助する事の問題点 新生児科医は生後30分以内のカンガルーケア(STS)にこだわるが、早期母児皮膚接触(STS)は児の体温が恒温状態に安定してから実施すべきである。その理由は、赤ちゃんの呼吸循環・消化管・肝腎機能・糖代謝などの調節を司る自律神経機能は、児が快適な環境温度で、しかも恒温状態に安定している時にしか自律神経本来の機能をまともに発揮する事が出来ないからである。日本産婦人科医会は出生直後のカンガルーケア(STS)を推奨するのではなく、恒温状態に早く安定させるための体温管理(保温)を優先する新生児管理法を会員に推奨すべきである。母親が出産後30分以内に母乳を飲ませられるように援助する事 つまり、生後30分以内のカンガルーケアが恒温状態への移行を遅らせ、心肺停止事故・発達障害児を増やしているのである。出生後に末梢血管(下肢)が最も収縮する時間帯、つまり赤ちゃんの中枢と末梢深部体温が最も離開する一番危険な時間帯(生後60分~90分)にカンガルーケアを行うべきでない。下肢の末梢血管が最も収縮する生後2時間の赤ちゃんは、一過性の低体温ショックの状態にあると考え、カンガルーケア(STS)を止め、保温(低体温の予防)に努めるべきである。 ◆赤ちゃんは何故泣くのか! 日本の寒い分娩室で出生直後の赤ちゃんは、身を縮め、手足は冷たく、筋緊張をたかめオギャーオギャーと激しく泣き出す。所謂、産声である。これらの赤ちゃんの行動と手足が冷たい理由は、放熱を防ぐために末梢血管を収縮(冷え性)させ、啼泣(筋緊張亢進+呼吸運動促進)によって熱産生を高め、より早く恒温状態に安定しようとする人間のもつ体温調節機構による生理的な現象である。つまり、出産直後の産声は、体温調節(産熱亢進)と肺呼吸の確立に重要な役割を果たしているのである。寒いとき、大人は震えるが、赤ちゃんは激しく泣くことによって熱産生を増やし、外界の低温環境に適応し恒温状態に安定していくのである。生後30分以内の“覚醒”の意味は、早期母子皮膚接触のための覚醒ではなく、末梢血管を収縮させ放熱を防ぐための体温調節機構によるものである。体温は末梢血管の収縮(放熱抑制)と拡張(放熱促進)によって調節されているが、収縮時に赤ちゃんは覚醒し、拡張時に寝るのである。赤ちゃんは “母子分離の不安”によって泣くのではない。 ◆出生直後のカンガルーケアにおける注意事項(日本産婦人科医会に対して異議) 日本産婦人科医会は、新生児の顔色や呼吸等の観察の重要性を認めているにも関わらず、顔色や呼吸等の観察が出来ないカンガルーケアを何故止めさせようとしないのか問題である。※ 臨床現場において、新生児の顔色や呼吸等の観察が出来ない新生児管理法は、イエロー・カード(黄信号)ではなく、レッド・カード(赤信号)である。日本産婦人科医会は、全国の産科医に「赤信号は注意して渡れ」と指導しているのである。また、母親(および家族)が「カンガルーケア」を理解し希望していることを確認した上で実施する。とあるが、母親が出生直後のカンガルーケアを希望したしても、「赤信号は渡ってはいけない」と注意を促すべきである。日本産婦人科医会は、ワーキンググループが作成した「カンガルーケア・ガイドライン」を、何の疑いもなく容認するのは危険すぎる。日本産婦人科医会は、元気に出生した赤ちゃんと産科医を事故(責任)から守るためにも、母乳育児3点セットの中止を、厚労省に訴えるべきである。 7.完全母乳哺育の短所(危険性) 母乳が出産直後から十分(基礎代謝量に相当する量)に出るのであれば、完全母乳哺育は積極的に推進すべきである。ところが、生後3日間の母乳分泌量は基礎代謝量の半分以下であり、特に出生初日はカロリー源としての母乳は殆ど分泌していない。完全母乳で哺育された赤ちゃんの問題点は、出生初日にどれだけの母乳(カロリー)を飲んだのか、母親にも、医療従事者にも全く分からない事である。赤ちゃんが乳首を上手に力強く吸啜したとしても、母乳が出ていなければ児の摂取カロリーはゼロとなる。生命維持に必要な最低限の熱量のことを基礎代謝量というが、新生児の基礎代謝量は50kcal/kg/dayと教科書にある。つまり、3Kgの新生児は150kcal/dayの熱量が必要となる。母乳の熱量は20mlで約13kcalであることから、3Kgの赤ちゃんは約220ml/dayの母乳を必要とする。しかし、初産婦で基礎代謝量に相当する母乳が出るのは、早くても3~5日目位からである。出生当日の母乳分泌は殆んど出ていないか、出ても滲む程度であることから、母乳からの栄養(カロリー)摂取だけでは、児は真に飢餓状態にある。※寒い分娩室に出生し、臍帯を切断され、母親からの栄養(糖分)が突然に途絶えた出生当日の赤ちゃんは、極度の低栄養状態(飢餓)にある事は間違いない。分娩室や母子同室中の寒い部屋で、新生児の低体温症を防ぐための体温管理(保温)を怠ると、児は熱産生に多くのエネルギー(糖分)を消費するため、飢餓状態の赤ちゃんはいつ低血糖症に陥っても不思議ではない。 完全母乳栄養児に飢餓熱が出たり、高Na血症性脱水に陥ったり、出生時からの体重が10%以上も減少するのは母乳が出ていない証拠である。新生児の低血糖症・低栄養(飢餓)が脳神経発達に永久的な障害を引き起こす危険性のある事は医学的常識であるにもかかわらず、寒い分娩室に生まれ熱産生に最も栄養(糖分)が必要な時期に、なぜ基礎代謝量に相当するカロリーを飲ませないのか、危険性を無視した完全母乳哺育と出産直後のカンガルーケアを推進する国(厚労省)の授乳と離乳の支援ガイドは大きな間違いを犯している。完全母乳とカンガルーケア(STS)にこだわる「赤ちゃんに優しい病院(BFH)」を、厚労省はなぜ支援するのか、厚労省はBFHに優しく、赤ちゃんに冷たい事を自覚すべきである。NICU不足を加速し、医療費が毎年増えるのは当然である。厚労省には、出生直後の赤ちゃんを心肺停止事故・発達障害から守る安全対策(予防医学)が無いのは重大問題である。 ※完全母乳哺育で、高ナトリウム血症性脱水の新生児が増加 赤ちゃんに優しい病院(BFH)認定施設病院である富山県立中央病院の田村賢太郎小児科医師グループは、「10%以上の体重減少をきたした完全母乳栄養児における高ナトリウム血症性脱水の発症状況」と題して、日本小児科学会雑誌 Vol.114, No.12, Page1896-1900 (2010.12.01) に論文を発表した。 要旨(論文引用) 母乳育児は世界中で広く勧められているが、近年,欧米から母乳栄養児が高ナトリウム血症性脱水に罹患し,時には致死的な合併症や神経学的後遺症を残したとの報告が散見される。より安全な母乳育児を推進するため,完全母乳栄養児における高Na血症性脱水罹患の頻度や特徴について検討した. 結果:主に10%以上の体重減少を来した母乳栄養児の4割弱に高Na血症が存在していることが示唆された. ※高ナトリウム血症性脱水を発症した母乳栄養児の半数以上で発達障害(トルコ) 同医師は高ナトリウム血症性脱水と発達障害との関係をkokluらの論文を引用し考察に次のように述べている。kokluらはトルコにおける6年間の調査で、入院を要する高ナトリウム血症性脱水を発症した母乳栄養児116人(Na中央値:166mEq/L,範囲:150~198mEq/L)のうち、半数以上で1歳以降に何らかの発達障害を認めたと報告した。また、血糖値については高ナトリウム血症群で低い傾向があり、今後の症例の蓄積が必要と述べている。結語に、母乳栄養に伴う高ナトリウム血症性脱水存在を認識し、特に脱水が疑われた場合には積極的な介入が必要であると研究結果を発表した。 ※生理的体重減少の“落とし穴” 生理的体重減少をどの程度まで許容するかについては一定の見解はない。アメリカ小児科学会は体重減少が出生体重の7%を超えた場合はなんらかの問題がある可能性があり、適切な介入が必要としている。一方、日本では、第1回 厚労省の「授乳・離乳の支援ガイド」策定に関する研究会で、生理的体重減少率の最低ラインは15%としましたと議事録にある。日本で完全母乳哺育をした赤ちゃんのほとんどが10%~15%の体重減少率があったと推測される。厚労省の完全母乳哺育は1993年からスタートしたが、その数年後から発達障害児が急に増え始めている事から推察すると、驚異的な増加傾向を示す発達障害(自閉症)の原因は母乳分泌不足つまり栄養不足(飢餓)に伴う高ナトリウム血症性脱水・低血糖症・低栄養・重症黄疸の赤ちゃんが急激に増えた結果と考えられる。 完全母乳を推進する新生児科医や助産師は、-15%までの体重減少率を生理的 現象と勝手に思い込んでいるが、体重減少率7%~15%の赤ちゃんは栄養不足の状態であったと考えられる。当院では、出生当日から基礎代謝量(50kcal/kg/day)に見合うカロリーを人工ミルクで補足しているが、体重減少率は平均2%前後で、5%を超える体重減少した新生児はほとんどいない。アメリカ小児科学会は体重減少率7%までを生理的現象としているが妥当な線引きと考える。 ※WHO/ユニセフの「母乳育児を成功させる為の10カ条」の第6条の短所 医学的に必要でない限り新生児には母乳以外の栄養(人工ミルク)や水分を与えないようにする。この第6条を忠実に実行すると、母乳の出が悪い生後3日間、特に初産婦の場合、殆んどの赤ちゃんが飢餓状態(基礎代謝量以下)にある。日本では生理的体重減少の定義が曖昧のため、生後数日間の低栄養状態の赤ちゃんが見逃されている。厚労省は生後一ヶ月検診時の体重増加を栄養状態の良・不良の指標にしているが、大事なことは母乳の出が悪い生後数日間の体重減少率をいかにして少なくするかを考えるべきである。母乳分泌不足による体重減少、つまり生後3日間の低栄養が児の脳の発育にどの様な害を及ぼすのかについての調査研究は日本に無い。完全母乳栄養の新生児は、生後3日間は飢餓状態にある。10%~15%までの体重減少は生理的現象ではなく、母乳分泌不足に伴う病的な体重減少である。完全母乳の落とし穴は、病的体重減少を生理的現象であると勝手に思い込んでいる事ある。 |
| 2012年5月21日 |
| |