| 早期母子接触の長所 “体温上昇作用” に科学的根拠なし |
※日本周産期・新生児医学会と日本産婦人科医会の発表に異議!
新生児科医からなるカンガルーケア・ガイドラインワーキンググループは、出生直後のカンガルーケア(STS)には、⑴体温上昇作用、⑵血糖値の安定、⑶呼吸循環の安定などの利点があると報告した。グループの一人である渡部医師(新生児科医)は、外国論文(ザンビア)の臨床データを引用し、カンガルーケアの体温保持作用について、「児の体温は保育器に収容するよりもカンガルーケアの方がより早く上昇し安定化する」を日本周産期・新生児医学界誌(第47巻、第4号2011年12月)に発表した。また、日本産婦人科医会幹事の鈴木俊治医師(葛飾赤十字産院院長)も渡部医師と同じ外国論文(Christensson 1998)を引用し、新生児の体温は保育器よりもカンガルーケアのほうが早く安定化すると第50回記者懇談会(2012年1月18日)で報告している。
下図 |
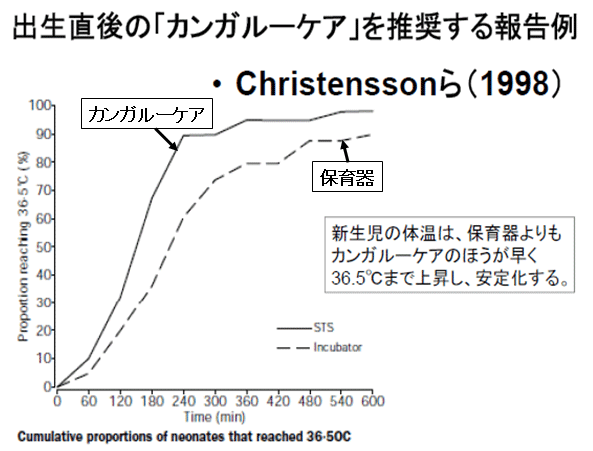 |
日本周産期・新生児医学会と日本産婦人科医会は、赤ちゃんが低体温症や手足が冷たくなった時は保育器に入れて治療するよりも、カンガルーケア(STS)で母親の体温で温めた方がより早く正常体温(恒温状態)に安定する。つまり、両学会は低体温症の赤ちゃんは保育器に入れる今迄の医療よりも、カンガルーケア(STS)で温めた方がより良い結果が出ると、医療現場に誤解を招く内容を発表した。
医学的常識を覆す両学会の今回の発表は、医療従事者(特に助産師)がカンガルーケアの体温上昇作用を信じ、冷たくなった赤ちゃんを保育器ではなくカンガルーケア(STS)を選択する事態が起こり得る。事実、新生児室で生後10時間目の赤ちゃんの手足が冷たくなり、冷たくなった赤ちゃんを助産師が母親の所に連れてきて、「手足が冷たいから抱っこして温めてください」、と言い残して助産師は部屋を出ていき、その後の観察もなかった。児は1時間後に心肺停止状態で見つかった。児は、一命は取り留めたが、現在、脳性麻痺の状態で、意識が無いまま人工的に呼吸管理されている。赤ちゃんに優しい病院(BFH)に認定された病院での出来事である。
⑴早期母子接触の “体温上昇作用”に、科学的根拠なし
日本の寒い分娩室においても、出生直後のカンガルーケア(早期母子接触) に “体温上昇作用”があるならば、「血糖値の安定化」・「呼吸循環の安定化」は信頼できる。しかし、早期母子接触に体温上昇作用がなければ、血糖値の安定化・呼吸循環器の安定化はあり得ない。日本周産期・新生児医学会および日本産婦人科医会は、日本の寒い分娩室においても出生直後の早期母子接触にザンビアの臨床データと同様の体温上昇作用があるかどうかを検証すべきである。出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)で事故が多発する理由は、ワーキンググループが日本の寒い分娩室で体温上昇作用を確認もせず、⑴体温上昇作用、⑵血糖値の安定、⑶呼吸循環の安定、などの利点があると発表したからである。
⑵ザンビア(後発開発途上国=最貧国)の臨床データの問題点
渡部医師・鈴木医師が引用した外国論文は、日本の寒い分娩室における正常成熟児の出生直後からのカンガルーケア(早期母子接触)のデータではなく、ザンビア(南アフリカ)の臨床データを引用しての報告であるところに問題がある。しかも、調査研究の対象は、正常成熟児の早期母子接触のデータではなく、主に早産児(平均33週~34週)、低出生体重児(平均1890g~2183g)であり、入院時の児の平均体温(直腸温)は34℃であったと記録されている。日本(先進国)の周産期医療の臨床現場に、後発開発途上国(ザンビア)における早産児、低出生体重児の臨床成績をなぜ参考文献として引用するのかが問題である。この論文は、出生直後のカンガルーケア(早期母子接触)の体温上昇説を裏付ける資料として不適切である。両学会は日本の寒い分娩室においても。早期母子接触に体温上昇作用があるかどうかを検証し国民・報道に報告すべきである。でなければ、心肺停止事故は繰り返され、さらに低血糖症に陥る赤ちゃんが増え発達障害児はさらに増え続けると予測する。厚労省は発達障害の原因と完全母乳・早期母子接触との因果関係について真剣に眼を向け対策を講じるべきである。
|
 |