乳幼児突然死症候群(SIDS)は着せ過ぎが原因
|
|
| 乳幼児突然死症候群(SIDS)は、わが国では「それまでの健康状態および既往歴からその死亡が予測できず、しかも死亡状況および剖検によってもその原因が不詳である乳幼児に突然の死をもたらした症候群」と定義されている1)。発症頻度は各国で異なり、出生児1000人当たり約6人から日本の0.5人前後とバラツキがある2)。その発症率の違いは各国の育児環境や診断基準の違い等にあると考えられている。1980年代の疫学調査でSIDS発症と育児環境との関連が指摘され、(1)うつ伏せ寝 (2)人工乳哺育 (3)保護者などの喫煙 (4)児の暖め過ぎの4つが危険因子として認められ、特にうつ伏せ寝が注目された。1980年代末から英国などを中心に「うつ伏せ寝中止運動」が始まり3)、その後1994年にはアメリカ小児科学会がBack-to Sleep Campaign(仰向け寝運動)の有用性を確認し4)世界中に広がった。その結果、世界のSIDS発生頻度は約50〜80%も減少した。 |
| |
| SIDSの問題点 |
| SIDSが抱える大きな問題はSIDSの原因が未だ不明であること。また仰向け寝でなぜSIDSの発生が減ったのか、うつ伏せ寝はなぜ危険なのかは依然として不明のまま。 |
| 日本では(1)うつぶせ寝 (2)煙草 (3)人工乳の3つを危険因子として取り上げた6)。その結果、発生頻度の減少は諸外国に比べ少なく、その理由としてわが国が危険因子から「児の暖め過ぎ」を除外した可能性も否定できない。 |
| SIDSのもう一つの問題は危険因子に人工乳が含まれていること。なぜなら、人工乳を危険因子として公表したため、それを心配した母乳分泌不全の母親が人工乳を与えなくなると赤ちゃんに栄養障害(重症黄疸・低血糖・新生児出血症などの主原因)7)を来す恐れがあるからである。そういったお母さん方が安心して赤ちゃんにミルクを与えられるためにも、SIDSの真の原因究明が急務である。 |
|
| SIDSを解明する |
| 1.SIDSの特長 |
| SIDSで死亡した児の特徴8,9)を表にまとめた。これらの特長のなかにSIDSの原因(疫学調査)と結果(剖検所見)が潜んでいると仮定すれば、すべての項目に共通した体温(温度)こそが本症と最も関連があると思われる。 |
| 表 乳幼児突然死症候群の疫学調査、剖検所見の特長(文献8.9より) |
|
|
|
| ● |
睡眠中の死亡である |
| ● |
年齢 : 生後4ヶ月をピークに1歳未満の児に多い |
| ● |
季節 : 夏より寒い冬に多い |
| ● |
室温が高温環境である |
| ● |
衣類(帽子・手袋・靴下等)、布団の着せ過ぎに多い |
| ● |
うつ伏せ寝に多い |
| ● |
人工乳の赤ちゃんに多い |
|
|
|
| ● |
死亡後、時間が経過しているにもかかわらず高体温の児が多い |
| ● |
発汗が認められる |
| ● |
血液 : 暗赤色流動性、高Na血症 |
| ● |
小腸 : 小腸粘膜に熱射病の際に見られるような組織の異常が観察される |
|
|
| 2.これまでの研究と原因 |
| SIDSの病因は、「睡眠時に起こる無呼吸から回復する防御機構である覚醒反応が、何らかの理由(未熟児、感染、気道の狭窄など)で遅延すると、ますます低酸素となり呼吸が抑制され悪循環におちいり死亡する」と考えられている10)。しかし、それがなぜ起きるのか/単一の原因かどうかなど未だに不明とされている。またうつ伏せ寝による乳幼児死亡の原因は「柔らかい寝具等による窒息」であるとしている研究報告もある。しかし、なぜうつぶせ寝が危険であるのか、その真の理由はわかってない。 |
|
| 3.赤ちゃんの体温調節について |
| 恒温動物である人間の赤ちゃんは、環境温度の変化に対して産熱と放熱のバランスを調節することによって体温の恒常性を維持している11)。赤ちゃんを詳しく観察すると哺乳や泣くこと(crying)によって多くの熱を産生していることがわかる7)。一方、放熱は主に皮膚からの伝導等や発汗によっ行われている。図1は生後2時間40〜6時間目の赤ちゃんの中枢/末梢深部体温/心拍数/行動(睡眠・覚醒・啼泣)を観察したもの。生後3時間目頃から↑印で示した間欠的な啼泣が観察され、それに一致した心拍数の増加とその後の中枢深部体温のわずかな上昇が記録されている。その後、児は睡眠に入り心拍数は120/分前後に安定し、末梢深部体温は次第に上昇(放熱)し、中枢深部体温は緩やかに下降している。生後4時間20分には中枢深部体温はわずかに下降し末梢深部体温と同じ(↓印:36.8℃)となり、それを境に赤ちゃんは突然激しく泣き出し、中枢深部体温は37.2℃まで再び上昇している。啼泣によって体温が37.2℃まで上昇したのちは、放熱のため末梢深部体温が再び上昇している様子がうかがえる。 |
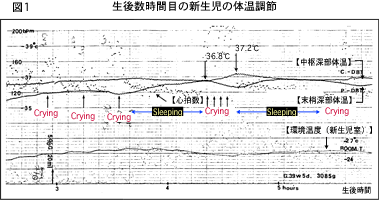 |
| 睡眠中の赤ちゃんの突然の啼泣は、中枢深部体温が下降(36.8℃)したために、寒さを感じた赤ちゃんが反射的に啼泣(筋肉運動)によって熱を産生していると考えられる。また、この啼泣は末梢深部体温が中枢深部体温より高くなるという通常では起こりえない体温の“逆転現象”を防ぐため、恒温動物としての安全装置が自動的に作動したものなのかもしれない。このように出生後間もない赤ちゃんにおいても、中枢と末梢の深部体温には収束と離開という鏡面像的な変動が認められ、これによって体温調節が営まれていることが理解できる。このとき赤ちゃんの心拍数の変動は血管収縮時に多くなり、血管拡張時に減少していることから、心拍の変動と末梢血管の収縮/拡張はカテコールアミン(CA)分泌と相関し、赤ちゃんの体温調節にはCA等の神経伝達物質が重要な役割を果たしていることが理解できる。 |
|
| 4.環境温度が赤ちゃんの心拍・呼吸に与える影響 |
| 高温から低温への経時的な環境温度変化のなかで、赤ちゃんがどのように体温を調節し、行動を変化させているのかを観察した12)。図2に示すように高温環境下では末梢深部体温の上昇(放熱促進)と睡眠/筋緊張低下(産熱低下)が認められ、低温環境下では末梢深部体温の下降(放熱低下)と体動や筋緊張亢進(産熱亢進)が認められた。呼吸機能としては呼吸数は変化せず経皮的酸素分圧(TcPO2)のみが高温環境下で低下した。この事実は、高温環境下では肺換気量が低下し低温環境時に比べより低酸素血症に陥りやすいことを意味している。さらに、低温環境(寒冷刺激)は呼吸機能を促進させ、睡眠からの覚醒反応を呼び起こすのに重要な働きを果たしていることがわかった。循環機能としての心拍数は、高温環境下では平坦で変動がなく、環境温度の低下とともに変動が増加し、特に啼泣に一致して頻脈が記録された。高温環境下、特に末梢深部体温の上昇(放熱状態)ではCAの分泌が低下していると考えられた。 |
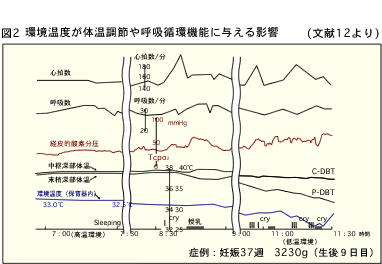 |
| 5.着せ過ぎが赤ちゃんの体温に与える影響 |
| これまで正常であった赤ちゃんが睡眠中になぜ高体温(うつ熱)になるのか。図3では新生児室の室温は26℃前後に空調されている。赤で示した布団内の環境温度は着せ過ぎ前では35℃〜36℃前後、着せ過ぎ後では次第に上昇し、放置していれば中枢深部体温まで高くなっていたかもしれない。さらに着せ過ぎが続けば中枢深部体温の上昇も起きたかもしれない。このように睡眠中の赤ちゃんは布団のなかで容易にうつ熱状態となり得る。赤ちゃんの放熱障害は環境温度と湿度の上昇で起こるが、赤ちゃんの環境とは室内の温度等ではなく布団や衣服内の温度と湿度を意味している。 |
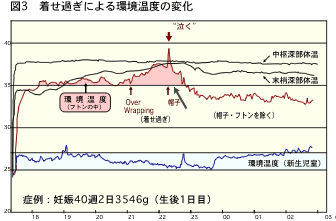 |
| 恒温動物は生きている限り産熱するが、死と同時に産熱が停止し体温は周囲の環境温度に影響される。SIDSの赤ちゃんの死体温度の高温は赤ちゃんの環境温度が高く、かつ環境が外部と熱の交流がなかったことを示唆している。さらに、うつ伏せ寝では末梢深部体温が容易に上昇することがわかった13)。その理由として放熱効果の高い腹部側を下にしたため放熱が妨げられ、その結果代償的に末梢(足底部など)からの放熱を増加させ体温を恒常に保とうとしているためである。もし、うつ伏せ寝の赤ちゃんに布団/帽子/靴下などを着せ過ぎていたら手足や頭部からの放熱障害が起こり容易にうつ熱となる。 |
|
| 6.SIDSの発生機序 -仮説-(図4) |
| 高温環境・放熱障害に起因した高体温(うつ熱)の場合には、発熱の際と異なり13)、体温を正常に保つために赤ちゃんは産熱を低下させる。つまり、うつ熱時に多くみられる睡眠・体動減少・筋緊張低下そして発汗などは熱産生を低下させ放熱を促進するための行動、すなわち赤ちゃんの体温調節そのものなのだ。うつ熱状態の赤ちゃんは通常よりも深い睡眠に陥り、同時に皮膚に対する“寒冷刺激”が欠如しているために睡眠からの覚醒反応は遅れ呼吸は抑制され、低酸素血症は次第に悪化する。さらに環境温度の上昇に伴う酸素消費量の増加という事態と相まって、睡眠中の赤ちゃんの低酸素血症は加速化され、生命維持装置(呼吸・循環)に非可逆性の異常が発生する。 |
|
| 考察 |
| 特に生後6ヶ月未満の乳幼児は「暑い」と言えないばかりか衣服を脱いだり寝返りも出来ない。寝返りや固い布団は、隙間を作り空気の出入りを良くし温度や湿度を下げている。(図3:左方の布団の中の温度の上下動)。さらに赤ちゃんが暑さに弱いということを知らない我々大人の着せすぎが、赤ちゃんを容易に高体温にする。冬の寒い時期には特にそうである。人工乳はやや熱くして(40〜45℃前後)飲ませるため、赤ちゃんが暖められやすくなると考えられる。ミルクの際にも必ず“抱っこ”して、赤ちゃんの高体温や発汗などの異常に注意しSIDSを未然に防ぐことが大事である。人工乳そのものがSIDSの原因ではない。着せ過ぎ等で放熱障害が起きた時とか、かつ眠っているときは、うつ熱、そしてSIDSはいつでも起こり得る。赤ちゃんは寒い時は目を覚まし泣き出す。しかし熱すぎる時は眠り続けたままなのである。 |
| SIDS予防には、保護者等に赤ちゃんが“暑さに弱い”ということを理解させることが必要である。うつ伏せ寝と着せ過ぎをやめさせ通気性や吸湿性の悪い衣服を着せたり不要な靴下や帽子を着せることは絶対に止めさせるべきである。また、赤ちゃんが眠っている時の手足の温度や発汗の有無に注意する指導が大切である。 |
| SIDSのkey wordsは、育児環境/着せ過ぎ/うつ熱/睡眠/寒冷刺激の欠如/覚醒反応の遅延/呼吸機能の低下/低酸素血症。赤ちゃんはSIDS(宿命的な病気)を持っているのではなく、異常な環境から逃げ出せないという特性を持っている。すなわち、SIDSは赤ちゃんの体温調節機能が理解されていないために起こった育児環境の誤りがもたらした結果と考えられる。 |
| 一方、SIDSのある専門医は「母親に罪の意識を持たせないために、SIDSは事故や過失ではなく疾患であることを理解させることが大切である」と病死説を取ることを勧めている14)死体検案医が病死と判断すれば剖検には家族の同意が必要となる。この2月に日本のSIDS学会から「SIDS・診断の手引き」が指針として発表された15)。この指針が少しでも強制力を有し、わが国でもSIDSに対してのEBM(evidence
based medicine)が実行され、さらに原因がが究明され、我々の仮説が検証されることを望まれる。SIDSで赤ちゃんを失った家族や託児所におもねった診断をすることは、SIDSをさらに闇で包むことになり、結果的にはSIDSでわが子をを失って悲しむ親を増やすことに他ならないと思える。SIDSはBack-to Sleep Campaignで減少したが、さらなる減少のためには、赤ちゃんの体温調節に関する研究をすすめ、厚生労働省、保健所、母親教室・学校などやメディアを通じての体温についての教育/啓蒙活動が重要である。 |
|
| 文献 |
| 1.平成9年度厚生省心身障害研究報告 |
2.Golding J,Limerick S.& Macfarlane
A.Sudden Infant Death.戸苅
創,
中里ピニングトン京子.訳.「乳幼児突然死症候群」.メヂイカ出版 ,大阪,1995 |
3.Wigfield,RE.,Fleming,PJ.,Berry.PJ.Rudd.PT.&
Golding.J.Can
the fall
in Avon's
sudden infant death rate be explained
by
changes in
sleeping
position?
Br Med J 304:282-283,1992 |
4.Commentary;Infant Sleep Position and
Sudden Infant Death Sundrome
(SIDS)
in the United
States:Joint Commentary from
Academy of
Pediatrics
and Selected
Agencies of the Federal Government.Pediatrics
93:820
,1994 |
| 5.阿倍寿美代.ゆりかごの死.新潮社,東京,1997 |
| 6.母子健康手帳(2000年発行) |
| 7.久保田史郎,安産と予防医学『THE OSAN』紀伊國屋書店福岡本店,福岡,2000 |
8.Bacon,C.,Scott,D.& Jones,P.Heatstroke
in well-wrapped infants
Lancet i:422-425,1979 |
9.Stanton,AN.,Scott, DJ.& Dowmnham,MAPS.Is
overheating a
factor
in some
unexpected infant deaths? Lancet i:1054-1057 ,1980 |
| 10.仁志田 博司.乳幼児突然死症候群.日本医師会雑誌122(4):591-596,1999 |
11.Kubota, S.,et al.Homeothermal ajustment
in the immediate
postdelivered
infant monitored by continuous
ans simultaneous
measurement
of core and peripheral body temperatures.Biol Neonate
54:79-85,1988 |
| 12.久保田史郎,他.新生児における体温変動の観察.産婦人科治療 39(4):463-469 (1979) |
| 13.久保田産婦人科HP:http.//www.s-kubota.net |
| 14.仁志田 博司.乳幼児突然死症候群.日本医師会雑誌125(8):136-138,2001 |
| 15.中山雅弘,他.乳幼児突然死症例・診断の手引き.日本SIDS学会雑誌1:63-83,2001 |
|
| * この記事は朝日新聞社及び筆者に無断で転載することを禁じます。 |
|
   |